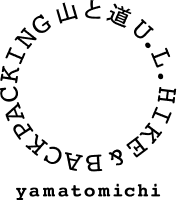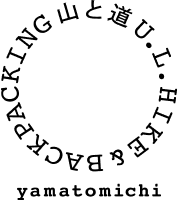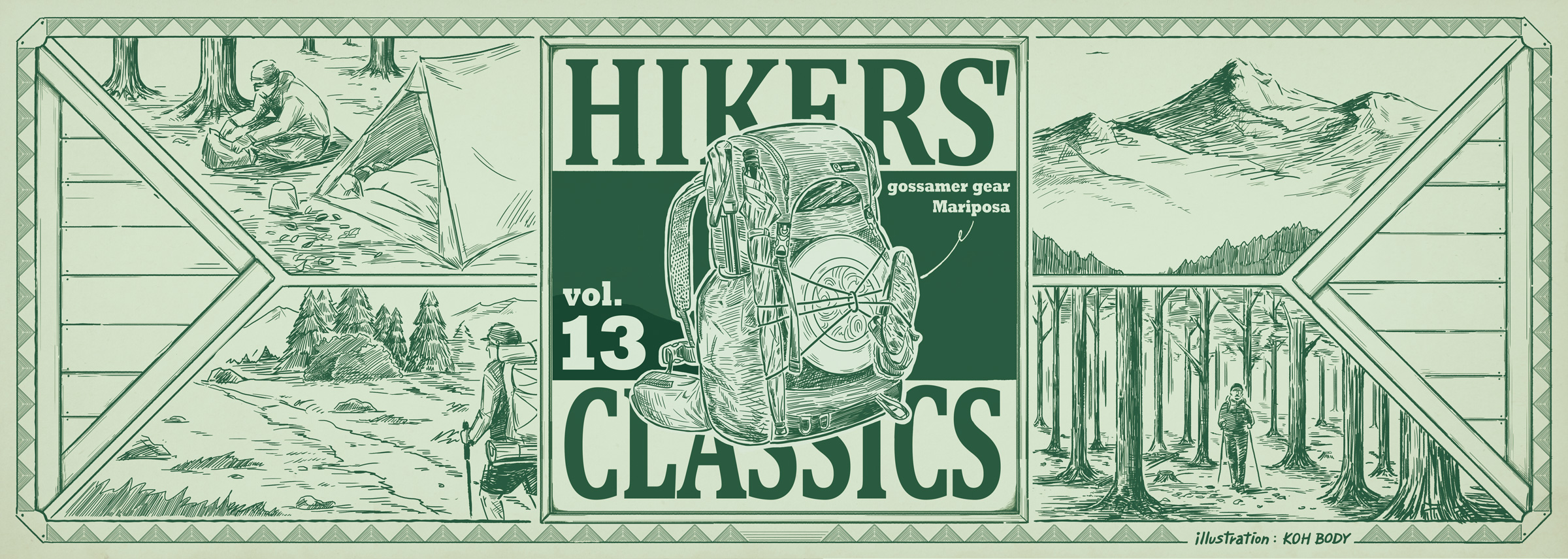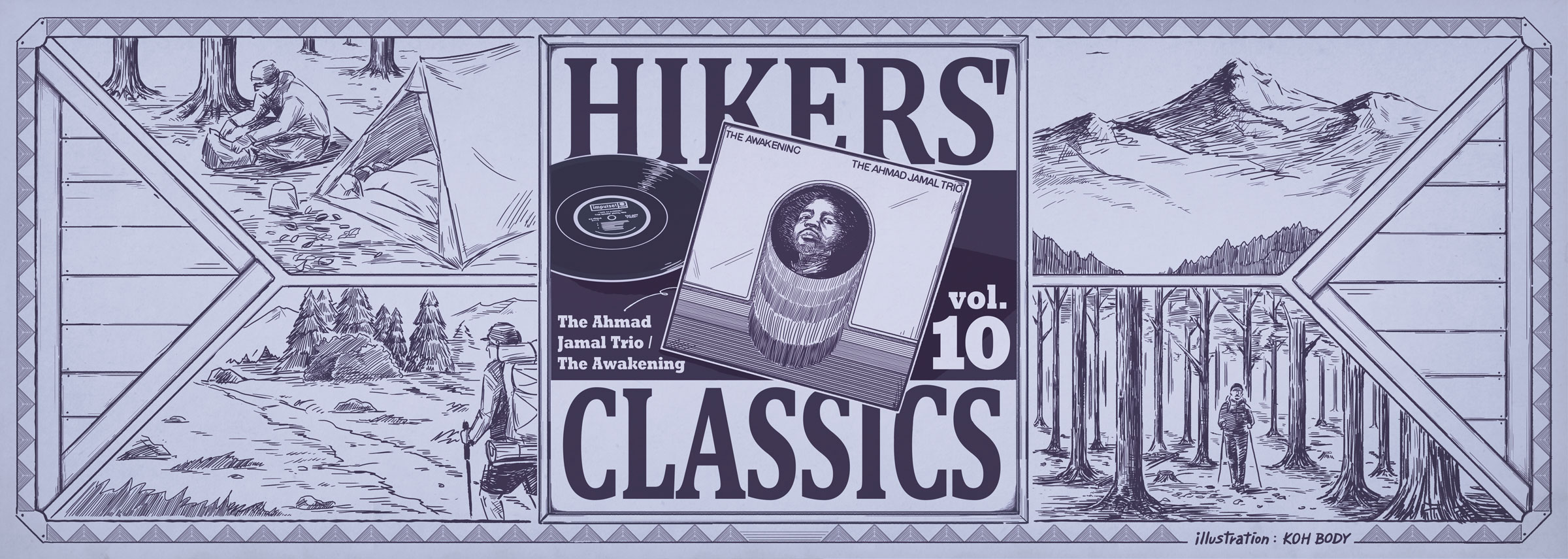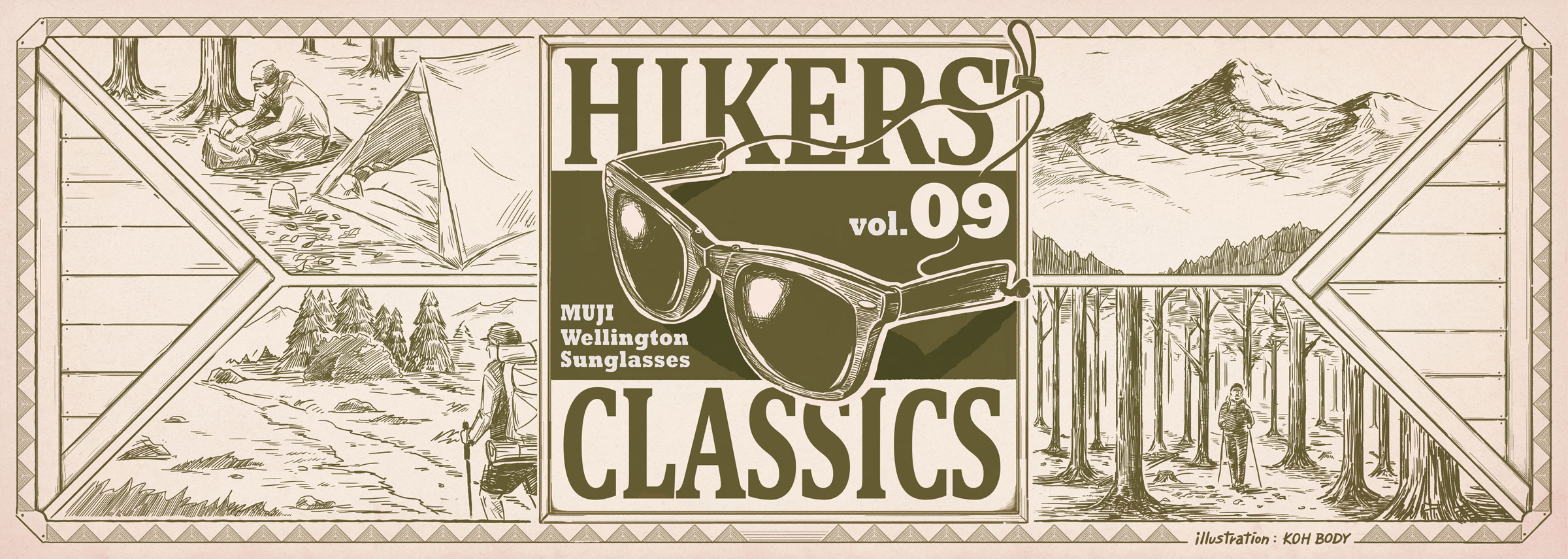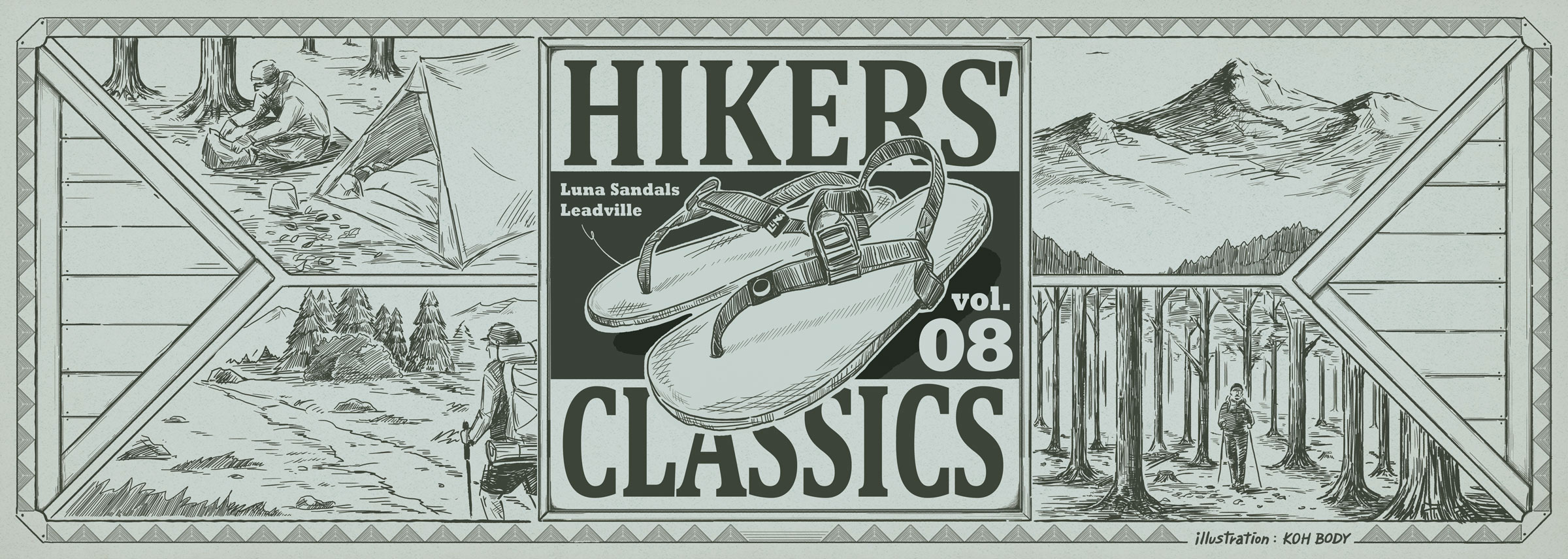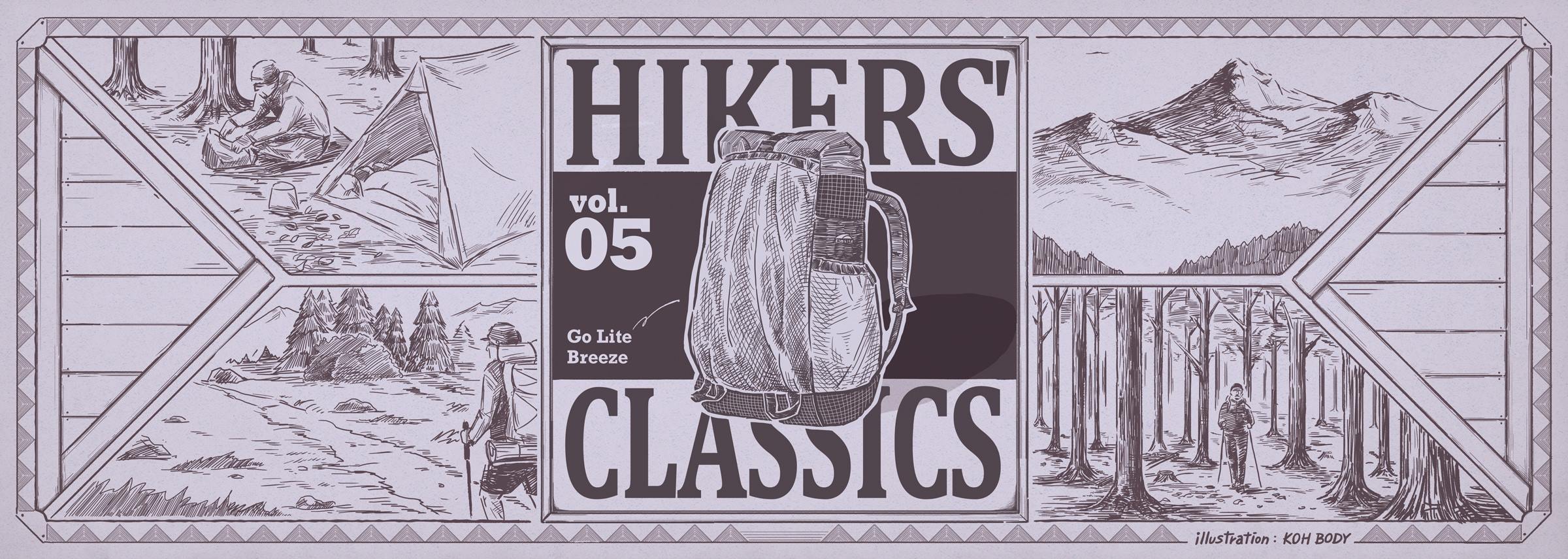誰にでもある、思い出の道具やどうしても捨てられない道具、ずっと使い続けている道具。
この『HIKERS’ CLASSICS』は、山と道がいつも刺激を受けているハイカーやランナー、アスリートの方々に、それぞれの「クラシック(古典・名作)」と呼べる山道具を語っていただくリレー連載です。
第4回目となる今回の寄稿者は、現在、数多ある日本のコテージメーカーの中でも、一際異端な物作りを行なっているGreat Cossy Mountainの「コッシー」こと大越智哉さん。日本のUL/MYOG/コテージシーンの草分け的存在であり、高校山岳部の時代からハイキングを続けるベテランハイカーでもあります。
そんなコッシーさんの挙げる「CLASSIC」は、どんなものなのか? Gコ山スピリット爆発の回になっています!
NOTE
僕が本格的にハイキングを始めたのは 1986年、15歳のときだ。 サッカーや野球は未経験だし、かといって帰宅部では時間を持て余してしまうという理由だけで、山岳部の扉を開いたのがきっかけだった。 当時の僕にとって、山岳部員であるということは、恥じることではなかったけれど、同時に誇るべきものでもなく、ただただ、「現場」であった。しかし、そこから卒業後も含めた1990年代にかけての数年間、実際に山へ行き、常に雑誌やカタログ、ショップでギアをチ ェックしていた経験は、確実に今に活きている。

1980年代後半の日本の山岳シーンと言えば、まだまだ大学山岳部と社会人山岳会がその中心だった。夏の北アルプスなどは、ニッカボッカにチロリアンハット、背にはキスリングや 背負子を背負った老若男女のパーティーや、今ではオールドスクールとも言えるようなミレーやカリマーのアルパインザックにラグビージャージとチノパンというスタイルのクライマー達で溢れていた。同時にヒマラヤブームや国内の難関ルートの初登争いも落ち着き、多くのクライマーは、 「次の何か」を模索していたころだったように思う。 当時、流行り始めていたフリークライミングもそのひとつだろう。
小川山や城ケ崎ではルート開拓が盛んにおこなわれ、平山ユージという天才クライマーが頭角を現した。 思えば、フリークライミングというスタイルの隆盛は、クライミングシューズの進化とカムデバイスの発明という「新しいギアの出現」がきっかけだった。ナチュラルプロテクション(岩場にボルトを打つことなく、割れ目にカムデバイスやナッツといった登攀器具を挟みこみ、それを回収しながら登ることで人工物を残さないクライミングスタイル)という、ある種の「思想」をテクノロジーの力が現実的なアクティビティへと昇華させた好例と言えるだろう。そのカムデバイスの生みの親であるレイ・ジャーディンが、同じように哲学的な思想をはらんだウルトラライトハイキングというスタイルの確立に大きく貢献したことは偶然ではないはずだ。

一方、僕はといえば、山岳部に所属し、定期的に山に行っていたとはいえ、そのような日本の山岳シーンとは全く無縁の清く正しい高校生生活を送っていた。僕の頭の中は、女の子とロックンロールが9割を占めていた。
そんな1980年代後半から1990年代前半にかけて、日本の山岳シーンは過渡期にあったといえるだろう。思い返してみれば、あの時期に、日本における登山スタイル、ひいてはアウトドアシーン全体に大きな変化が起こった。誤解を恐れずに言えば、アウトドアのファッション化だ。そして単なるスポーツやレジャーであった登山も、カルチャーとして語られる場面が増えてきた。守るべきものと変えていくべきもの、両者が入り乱れ、ちぐはぐなアウトドアスタイルがストリートファッション化し、「アウトドア」という、掴み所の無い、得体のしれないものを食い扶持にする大人たちが沢山現れた。 僕にとっても、趣味というよりも、あくまで「現場」であったアウトドアが、女の子やロックンロールと同じようにとても大事な、意味のあるものに変わっていった。

1989年、目白にパタゴニアの直営第1号店が開店したことはとても大きなトピックであったし、「渋カジ」や「アメカジ」といわれるファッションスタイルは、最初は鼻で笑っていたアウトドアマンにとっても無視のできないものになっていた。「新しいギア」は、その革新性や使い勝手以上に、その素材や思想的な背景が多く語れるようになる。このような流れに批判的な人々も多かったように思う。しかし、少なくとも僕にとっては、「ギアとは何か?」を真剣に考える大きな好機であったのは間違いない。ざっくりと1990年をひとつの転換点としたとき、それ以前とそれ以降で、大きな違いがあるのは事実であろう。素材やテクノロジーの進化はもちろん、ファッションという荒波に揉まれ洗練された姿が1990年以降のギアには見え隠れする。
しかし、一方で1990年以前から脈々と続く遺伝子のようなものを内包したギアが今なお作り続けられているのも事実である。そして、僕自身が魅力を感じるのも、その遺伝子の部分に他ならない。1990年以降に本格的にギアの魅力に気づいた僕が心惹かれるのは、実は1990年以前から続く遺伝子の部分であったというのはとても皮肉な話だ。

1991年、オルタナティヴロックのアイコン的存在であるニルヴァーナが大ヒットアルバム 「NEVERMIND」をリリースする。あれから四半世紀以上の時が流れた。今の若者にとってニルヴァーナはオルタナティヴであるのか? それともクラシックなのか? その問いに、僕はあえてこう答えたい。
「クラシックの無いところにオルタナティヴは生まれないし、オルタナティヴなものしかクラシックとして生き残らない」と。