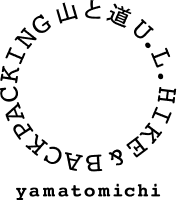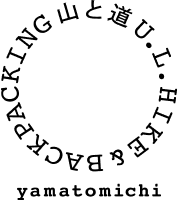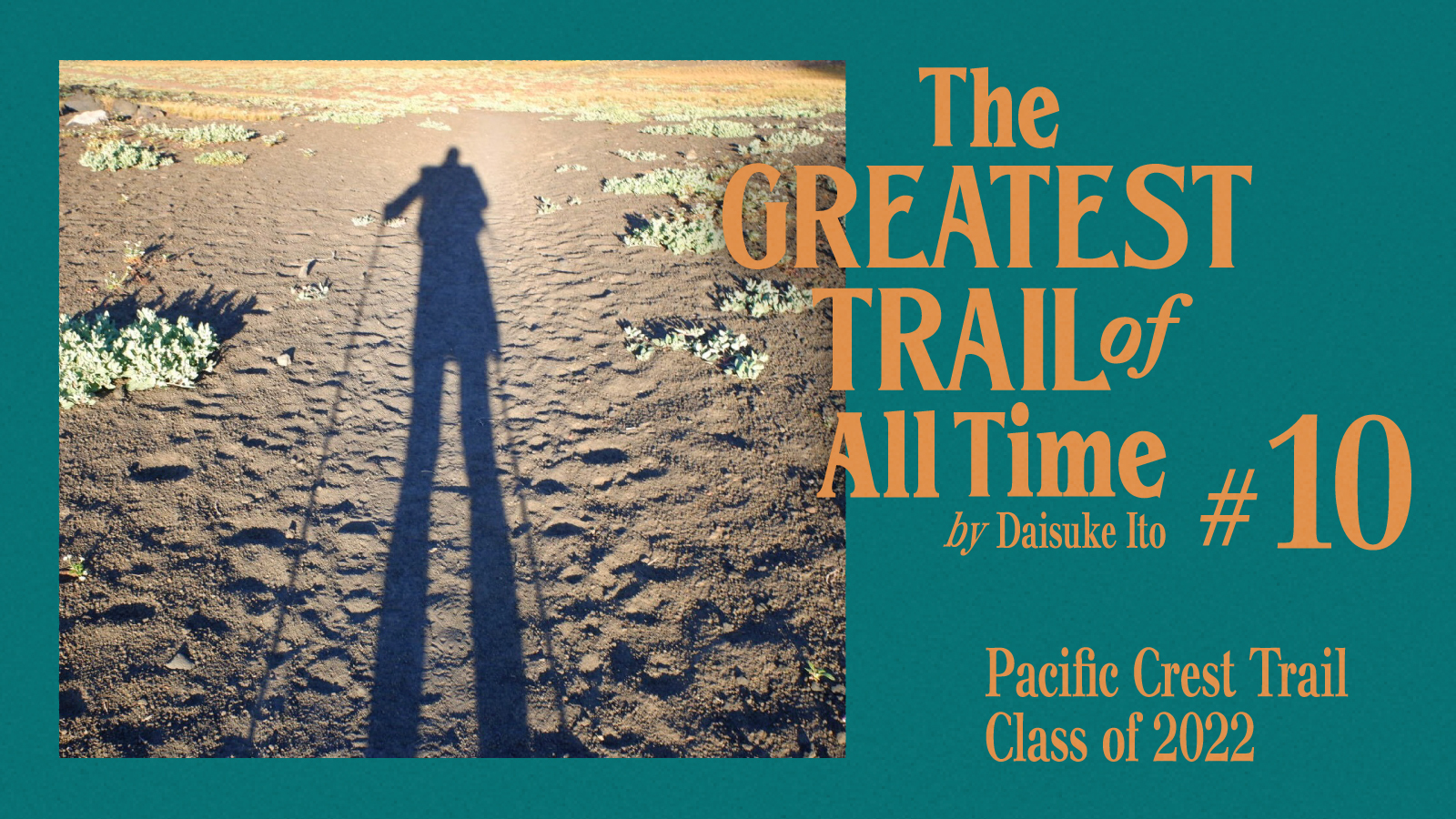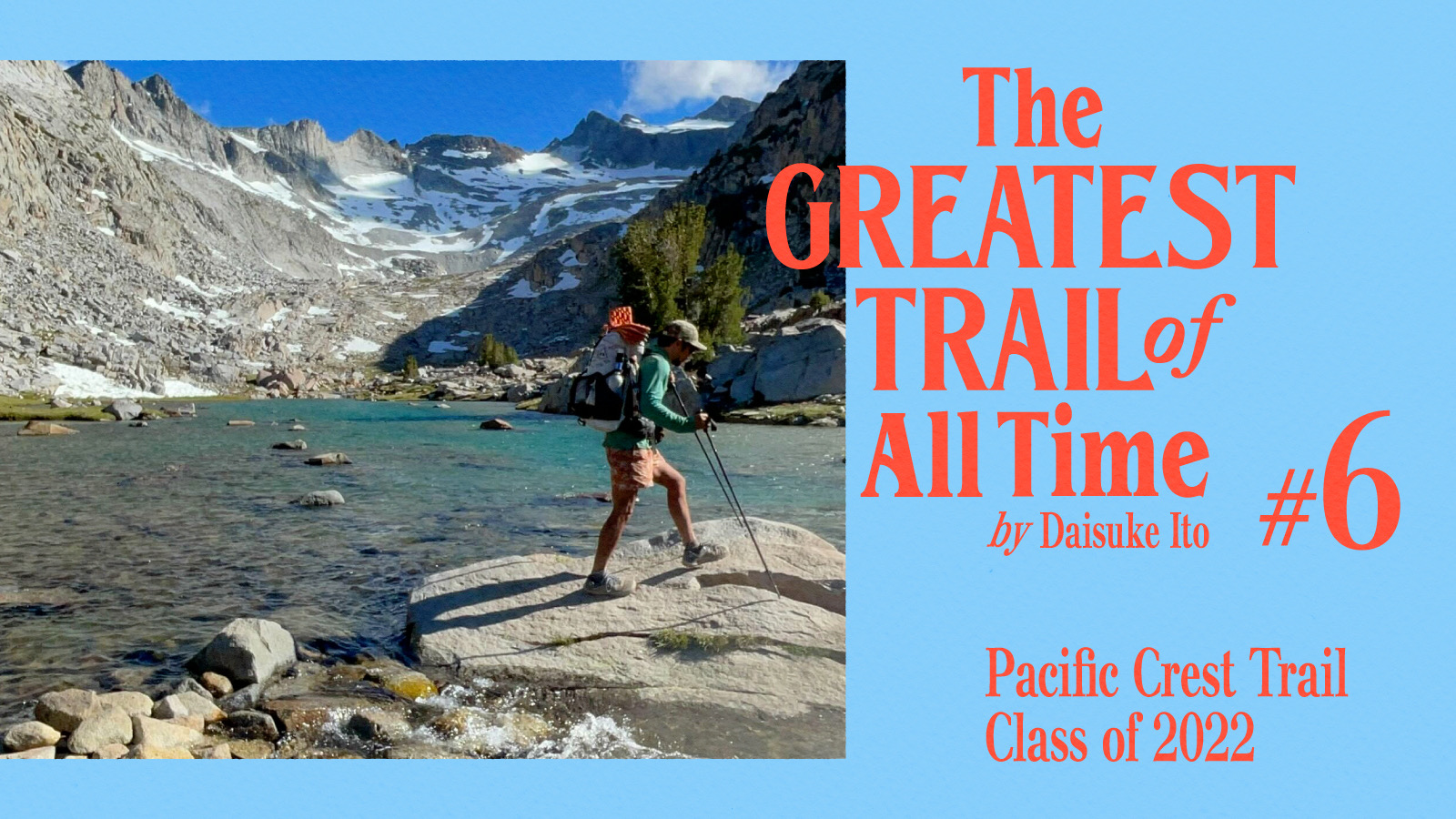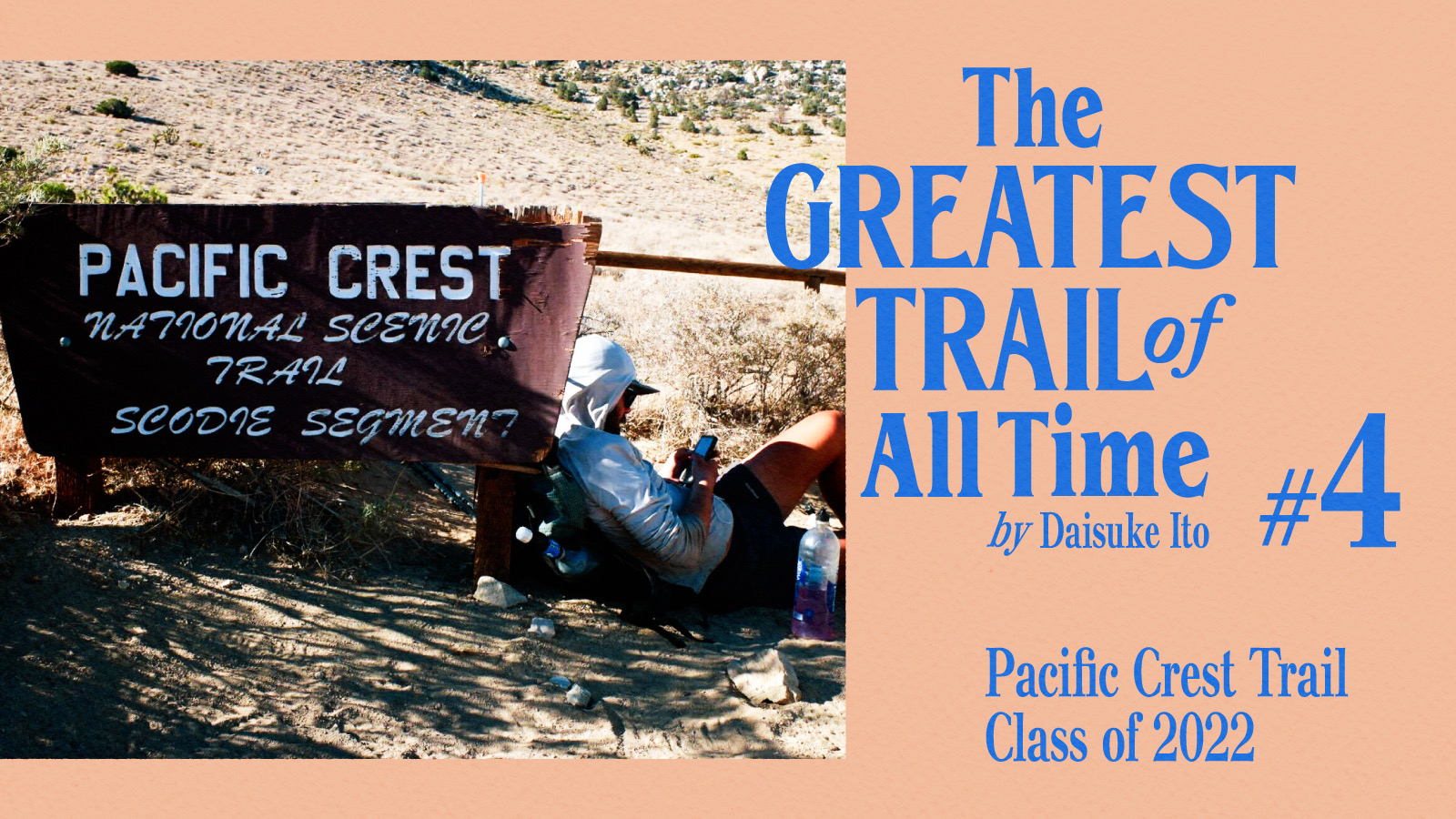#5 シエラの脅威、そしてもたらされた絆
#5 シエラの脅威、そしてもたらされた絆
メキシコ国境からカナダ国境まで、アメリカ西海岸の山々や砂漠を越え4,265kmに渡って伸びるパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)。「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大トレイルのひとつであり、さらにウルトラライト・ハイキングそのものも、そこを歩くハイカーの中から生まれてきた正にULの故郷とも言えるトレイルです。
そんな「ロングトレイルの中のロングトレイル」PCTを、山と道京都スタッフ、伊東大輔が2022年にスルーハイクした模様を綴る全10回の連載の#5。今回、PCTのハイライトのひとつであるシエラネバダに辿り着いたトレイルネーム「ゴート」こと伊東は、仲間と共に予想外の雪の猛威に遭遇します。さらに絶景を行く一行には思いがけぬ再会もあり、パーティの形も微妙に変わっていき…。
警鐘
3,000mを越える高山がひしめくシエラネバダ山脈(以下、シエラ)は、これまで歩いてきた乾燥地帯とは漂う空気がどこか異なり、トレイルの側には生命力溢れる巨木が、空に届きそうなほど力強くそびえ立っている。アウトドア好きなら一度は聞いたことのあるだろうヨセミテ国立公園やセコイア国立公園もシエラの一部であり、まさにアウトドア天国と呼ぶにふさわしい場所だ。ぼくたちはPCTの南カリフォルニアに広がる乾燥地帯を越え、待ちに待ったシエラへと足を踏み入れた。
シエラの玄関口、ケネディメドウズを出発したターザン、ウォーターボーイ、ぼくの3人は、アメリカ本土最高峰のホイットニー山を経由して、ビショップまでの約180kmを7日間で歩く予定を立てていた。ホイットニー山はPCTのルートから10kmほど逸れるのだが、そんな名峰を無視できるはずもない。
「シエラに入って数マイル歩いただけで、こんなにも景色や気候が変わるのって不思議だと思わない?」
日本でいうところの北アルプスのような憧れの場所に浮かれるぼくが、あたかも新しい発見をしたかのようにそう言うと、ターザンがどストレートの正解を投げ返してきた。
「標高が上がったからだろ?」
……ごもっともだよターザン。

段々と標高を上げていき見える景色が変化してきた。

倒れた巨木にもたれかかりひと休み。ターザン、君は何を見つめているんだい?
シエラを歩き始めて3日目の朝早く、テントにポツポツと打ちつける嫌な音で目を覚ました。
日本では慣れっこの雨のアラームだが、アメリカのそれにはたいそう気分が落ち込んだ。PCTを歩き始めて1ヶ月半ほど経つのだが、なんと初めての雨だった。テントの隙間から仲間たちの様子を覗いてみるが、彼らのテントは静かに佇むだけなので、現実から逃げるように再びまぶたを閉じた。
これくらいの小雨なら、次に目を覚ました時には、何事もなかったかのように青空を覗かせているだろう。これまでも全く雨が降ってないのだから、きっとそうに違いない。
ぼくはテント内に響く誇張された雨音から耳を塞ぐように眠りについた。

日が暮れ始めて赤く染まりはじめるシエラ。
再び深い眠りから覚めると時刻は午前9時を回っていた。ぼくの期待は叶わず雨は振り続けており、早朝と変わらぬよどんだ景色にため息をついた。
重い腰を上げたぼくたちは荷造りを済ませ、しぶしぶ歩き始めたのだが、雨は標高を上げるに連れてなんと雪に変わってきた。
「もう7月だよな? こんなの聞いたことないよ…!」
高山地帯なので夏も残雪はあるが、この時期の降雪なんて聞いたことがない。この先はホイットニー山へとトレイルは続き、シエラの核心部へ足を踏み入れるので、3,000mをゆうに越える山岳地帯を3〜4日は歩き続けなければならない。この異常事態にあたりを巡回していたレンジャー(国立公園の自然保護官)からは、明日はもっとひどいスノーストームの予報だと聞かされた。
「戻った方がよくないか?」
一度歩いてきたトレイルを引き返すのはどうも気が引けるが、この先に進むことが良策とは思えず、2人をどのように説得しようか考えはじめた。そんな非常事態にも関わらず、ターザンとウォーターボーイはぼくの遥か先にいた。歩くペースが違うので、トレイルではぐれることは日常茶飯事なのだが、こんな日くらい一緒に歩いていればよかった。もしこのまま彼らと会えなかったらぼくはどうすればいいんだ?
そうは言ってもPCTは一本道。
「彼らに追いついて今すぐ相談しなくちゃ……!」
心静かでないぼくは、ほっぺたに吹き付ける冷たい粉雪をぬって、視界の悪いトレイルをギアを上げて歩き進めた。

空から舞い降りてきた粉雪にトレイルは白づきはじめている。
白化粧されていくトレイルに急かされ、1時間ほど行くとトレイルの脇に見慣れたテントが視界に入ってきた。
「もしかしてターザンかい?」
そう声をかけると聞き慣れた、しかし力のない弱々しい声がぼくの元へ返ってきた。
「オレだよ。全身びしょ濡れでもう動けないぜ……」
「なんだって⁉︎ 大丈夫かい?」
しっかり者でリーダー的な存在の彼が、ここまで弱ってしまっていることに焦りを隠せなかった。荷物を極限まで削ったULハイカーの彼は、レインジャケットは簡易的なもので、レインパンツに関しては持ってもいなかった。そんな状態で降雪にあったものだから、全身に冷たい雪をまとってしまい、低体温症のような状態に陥っていた。
「しばらく動けそうにないから先に行ってくれていいぜ。引き返すなら早めに戻った方がいいだろう。」
「いや、そんなことできるわけないだろ! ……ってちょっと待て。ウォーターボーイには会わなかった?」
思い返すと、ターザン→ウォーターボーイ→ぼくの順番で歩いていた。ターザンも彼を見かけていないようで、おそらく木かげのターザンのテントに気づかず先へ進んでしまったようだ。山深いエリアで電波もないので、動けるぼくに残された選択肢はひとつしかない。
「ターザン、ちょっとここで待ってて。ウォーターボーイを捕まえに行ってくる!」

降り続く雪は美しく、しかしぼくたちに不安を与えた。
ウォーターボーイとはついさっきまで一緒にいたので、急いで追いかければすぐに見つかるだろうと考えていたが、いつまでたっても彼の姿が見えてこない。捕まえると言ったものの、トレイルから見えない木かげで休憩していたり、用を足すのに茂みに入っていて、ぼくが彼を追い抜いてしまえば……この先は考えたくもない。
もちろんぼくも余裕なわけではない。
無情に降りつける雪の中を歩き、びしょびしょに濡れた手足はかじかみ、逃げ出してしまいたくなるほど、ぼくの心は疲弊していた。
「あぁ、寒いなぁ……もうどうしたらいいのか分からないよ……」
ターザンと別れて2時間ほど歩いた頃だろうか。不安でパンクしそうなぼくの目の前にうっすらと希望の光が差し込んできた。トレイルの側にビバークする数十のテントが張られており、その中にウォーターボーイのテントと同じものを見つけたのだ。
「ほんとうに頼む。そこにいてくれウォーターボーイ。」
いまにも心が折れてしまいそうなぼくは、神にも祈るような思いで、雪に覆われたテントを覗き込むと、そこには寝袋にくるまるウォーターボーイの姿があった。
「……おお、ゴートか。」
小さく体をまるめる彼を抱きしめたくなったが、ここでゴールではない。彼にここまでの経緯と撤退すべきことをつたない英語で必死に伝えたが、彼もターザン同様にかなり参った様子だった。
「ゴートが言う通り引き返した方がベターだな。でもすこし時間をくれないか? ゴートもテントを張って暖を取った方がいいよ」
まだまだ予断の許さぬ状況なのだが、なんとか3人一緒になれそうな安堵感から緊張の糸が切れ、体が急に冷えてきた。すばやくテントを設営して乾いた服に着替え、寝袋に飛び込んだぼくは、いつしか眠りについていた。

ついには雪に埋め尽くされたトレイル。どうしてそんなに笑顔でいられるんだ?
「お〜い、ゴート、ウォーターボーイ。街に戻るぞ〜!」
寝ぼけたぼくはまだ夢の中かと思ったが、テントの外を覗くと確かに元気なターザンの姿がそこにあった。心と体を落ち着かせた彼はいても立ってもいられず、ぼくたちを探しにトレイルを進んできたそうだ。
「さっきは悪かったな。気持ちがナーバスになってしまっていたよ。」
いつものターザンが帰ってきた。
普段から顔を合わせる仲間が、普段と変わらぬ表情でこちらを向いているだけで、もう危険が過ぎ去ってしまったかのように心の荷が降りた。
山の状況は先ほどとなんら変わっていない。
むしろ降り続く雪はその勢いを弱めることなく、あたり一面を白く覆っている。落ち着いている暇なんてどこにもあるはずないのに、ぼくの心の中には明らかな余白がうまれていた。
「ここから最短の登山口までは……そうだな、30kmくらいか。」
時刻は14時をまわり、今日中に街へ戻ることはできないだろうが、できるだけ登山口のほうへ戻っておく方がいいだろう。急いでバックパックに荷物を詰め込んだぼくたちは逃げ出すように白銀のトレイルを後にした。

実はスノーストームでスマートフォンが水没してこの時の写真がほとんど残っていないのだ。写真はターザンとウォーターボーイ。

画質は悪いが唯一残っていた3人の写真。思い出に画質なんて関係ないよね。
翌日の昼下がり、無事に登山口に戻ったぼくたちは、街へと向かうバスに揺られていた。車窓に広がるシエラは、昨日までの悪天候が嘘だったかのように、穏やかな表情をのぞかせている。どうやら「今日はもっとひどいスノーストームになる」という、嫌な予報は的を外れたようだ。
「ここのバーに行けばビリヤードもあるぜ!」
「街についたらマクドナルドにいこう! 」
隣に座っているターザンとウォーターボーイは一息つく間もなく、地図アプリで街の娯楽をチェックしている。切り替えの早さに驚かされながらも、いつも通りの彼らの笑い声に包まれていることに、ぼくの表情は和らぎ、彼らと一緒にいられる普通に幸せを感じた。思い返すとこの出来事がぼくたちを「仲間」から「バディ」に変えたのかもしれない。
ここまでメキシコ国境から1,000km以上の道のりを歩き、ちょっぴり自信がついてきたぼくたちに、「そんな上手くいかないぞ」と、常に危険と隣あわせであることを自然が教えてくれたかのようだった。
はたしてぼくたちは無事にシエラ、そしてPCTを歩ききることができるのだろうか?
一難を乗り越えてホッと落ち着いたかのように見えたぼくの胸の奥では、いままで以上にPCTが大きな壁に感じられていた。

街ではシエラの恐ろしい記憶を塗り替えるかのように遊びまくった。

果たしてこの先のシエラはどんな表情でぼくたちを待ち構えているのだろうか。
リスタート
まばゆい太陽の光に目を細め、段々と希薄になっていく空気に呼吸を乱されながら、まるで別の惑星かのような場所に辿り着いた。森林限界をゆうに越えたその場所は視界を遮るものがなく、東には砂漠にポツンと広がる街、西には魅惑の岩肌を見せびらかすゴツゴツとした山々を見渡すことができる。
ここはアメリカ本土最高峰、標高4,418mのホイットニー山の頂。
ホイットニー山はシエラを代表する山で、PCTと重複してこのエリアを走るジョン・ミューア・トレイル(JMT)の終着地点にもなっており、さまざまな肩書きのハイカーが入り混じっている。
5日前にスノーストームで撤退を余儀なくされたぼくたちは、再びトレイルに戻ってきていた。その時の降雪は幻想だったかのように、トレイルは元気に顔をのぞかせ、雲ひとつない晴天はこの場所への登頂を祝ってくれているようにも思えた。
用意された ”MT. WHITNEY 14,505” のプレートを上下左右に構え、満足いくまで過剰な記念撮影を終えると、午前4時から行動していたぼくはぐったりと大きな岩の上に寝そべった。
陽に照らされた岩がほんのりと暖かく、空がどこまでも青くて綺麗だ。いまのぼくにとってはそんな当たり前がすごく幸せに感じた。
数日前とは時の流れ方がまるで違う贅沢なひとときを、ぼくは忘れることはないだろう。

”MT. WHITNEY 14,505”のプレートと記念撮影。

まるで別の惑星のようなトレイルが続く。

雪解けでつくられた湖と岩が形成する景色は圧巻だ。
シエラの世界はまさにアメとムチだ。
湖と岩、そして木々のコントラストが素晴らしく、幾千ものハイカーを虜にしてきた景色が、一瞬たりともぼくを飽きさせない。
「あ〜もう! なんでこんなにきついんだよ。腹立つな〜!」
それと同時に毎日必ずやってくる、時には15kmも続くような急登に文句を吐き捨て、峠の向こうにある語彙力を失うほどの絶景に黙らされる、そんな忙しい毎日を過ごしていた。
そんなぼくたちにとある変化が訪れた。
バディのターザン、ウォーターボーイとはこれまで50マイルチャレンジや水源汚染エリア、シエラのスノーストームの大波を乗り越え、徐々にお互いの絆、そして旅のカタチを固めてきた。そこにパピーというハイカーが加わることになったのだ。
以前から「あなたたちと一緒に歩きたいわ!」と言ってくれていたのだが、微妙にタイミングが合わずにそれは叶わずにいた。しかし、スノーストームによる撤退で彼女がぼくたちに追いつき、共に行動をすることになった。彼女とはかれこれ1ヶ月以上の付き合いで、何度もトレイルや街で顔を合わせている馴染みのハイカー。気さくでまわりを明るくしてくれる彼女とハイキングができることを楽しみにしていた。
その一方、ぼくの頭の片隅にはある不安が離れずにいた。
「シエラはとても楽しみにしていたエリアなの。1日20kmくらいでゆっくり歩くのがちょうどいいわ。なんなら10kmでも十分よ。」
彼女はこう言うのだが、ぼくたちはシエラのエリアを1日30kmほどで計画しており、どうもペースが合いそうにない。それにぼくの考えは彼女とは異なり、ゆっくり歩く=楽しめるではない。早く長く歩いていても十分に景色は楽しめるし、むしろ歩くときはしっかり歩くことで心に余裕が生まれ、心に引っかかりのない「楽しい」ハイキングができる。急いでいるわけではないのだが、ゴールのカナダ国境へは9月末の降雪前に辿り着かなくてはならず、前へ進むということは、ぼくたちハイカーの唯一の決まりごとだ。
そんな懸念は的中し、ぼくたちのハイキングスタイルはカタチを変えていくことになる。
優しいウォーターボーイは遅れる彼女のペースに合わせて後ろを歩くことが多くなり、ターザンはそれを理解できずに彼らから離れるようにペースを上げ、みんなが顔を合わせるタイミングが徐々になくなっていった。上手くいっていたバランスが音を立てて崩れたかのようで、彼女の存在に疑問を持たなかったと言えば嘘になってしまう。
そうは言っても彼女にはなんの非もない。
彼女は自分の歩きたい人と、歩きたいペースで、自分らしく旅をしている。ただそれだけだ。それが旅人のあるべき姿だと思う。ぼくたち3人も自分の心に従い、自由気ままに旅をしている。歩くペースや行動のパターンが似ているからこそ、他人に合わせることなく自分らしく旅をしていられただけに過ぎない。
ハイキングのバディは性格や人柄はもちろんだが、行動パターンや歩くスピードが似ているということも非常に重要だ。せっかくの自分だけの旅、こんな異世界に飛び込んできているのに、人に合わせる必要があるのだろうか。自分の意思をどこかに隠して、我慢するような旅なんてごめんだ。
そんなことを思いはじめた頃、この刻を見計らったかのような再会が訪れる。

仲間たちとの一枚。どんな綺麗な景色よりも思い出深い。

湖にうつる山々。シエラの景色が素晴らしすぎてここに写真を載せきれないのが残念だ。
ふたつの再会
4人で行動し始めて、1週間ほどがたった。
残雪のトレイルを注意深く歩き進め、標高3,648mのミューアパスへ辿り着いたぼくたちは、そこでランチブレイクを取ることにした。この場所には、ミューアハットという名の知れた石造のシェルターが建てられており、ちょうど昼時に差しかかっていることも相まって、多くのハイカーが腰を掛けていた。
「今日はもうデカイ登りはないよな?」
「キャンプ地まではあと何kmだ?」
そんないつも通りの会話をしていると、向こうのハイカーのグループに見覚えのある顔を見つけた。
「もしかして……ブランドンかい⁉︎」
彼とは1日目にPCTサウザンターミナスに向かうバスで会って以来、なんと1ヶ月以上ぶりの再会だ。言葉を交わす間もなくハグをしたぼくたちは、積もりに積もったこれまでの旅のことをお互いに話し、それはまるで昔の同級生と話すような感覚だった。
どうやら彼は序盤で足を怪我してしまったそうで、しばらくトレイルを離れていたようだ。それでもリタイアを選ばず再びトレイルに戻ってきた彼のトレイルネームはフェニックス(不死鳥)。いかした名前じゃないか。
1ヶ月以上もの間、旅にもまれ続けてきた彼の目は、ぼくを飲み込んでしまいそうなほど、力強さを増していた。

ミューアハットの前で記念撮影をするブランドンとぼく。

残雪の中を注意深く進む。
そしてミューアパスはぼくにもうひとつの再会を用意していた。
あるハイカーが待ち合わせに遅れてきた仲間かのように、ひょっこりとこの場所に現れた。
ストレッチだ。
彼とは50マイルチャレンジを共にしたのだが、ぼくたちよりも先にトレイルに戻っていたので、正直もう会えないんじゃないかと思っていた。
彼は24歳と若く、体力も抜群で、185cmはあろう身長と長い足を武器にスピード感のあるハイキングをする。50マイルチャレンジでもほとんど彼の姿を見かけないほど、ぼくたちに差をつけて歩き切っていた。大好きなハイカーのひとりなのだが、とてつもないスピードで歩く彼には追いつけるわけないと、心の中で別れを告げてしまっていた。
しかし、家庭の都合で一旦トレイルを離れていたので、いまこうして再会できたというわけだ。ストレッチはここでぼくたちと落ち合う予定でいたかのように、自然とぼくたちの輪に加わった。

再会したストレッチもぼくたちと行動することになった。
スノーストームや新しい仲間の加入で、時の流れが微妙にねじれて、ふたつの再会をもたらせた。
この出会いは偶然なのか、はたまた必然か。
それは旅を終えた時に判断することにしよう。
YouTube
伊東とスタッフJKが旅の模様をYouTubeでも振り返りました。