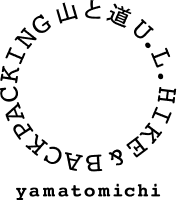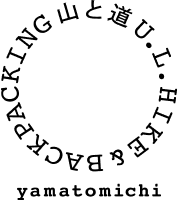スケッチが帰ってきた!
アメリカの3大トレイルを制覇したトリプルクラウン・ハイカーであり、この山と道JOURNALSでもコンチネンタルディバイドトレイルやアパラチアントレイルでのスルーハイク記を連載してくれたトレイルネーム「スケッチ」こと河戸良佑さん(近年ではソックスブランドHIKER TRASHディレクターとしてもお馴染みかもしれません)の、今回の行き先はアリゾナ。メキシコ国境からユタ州との州境までアリゾナ州を南北800マイル(約1,280km)に渡って縦断するアリゾナトレイルを52日間かけてスルーハイクしたストーリーを、短期連載という形で今回も寄稿してくれることになりました。
前述の通り、前回のアパラチアントレイルでトリプルクラウンを達成し、もはやスーパーハイカーの仲間入りをしたと言っても過言ではない彼ですが、それでもやはり、スケッチはスケッチ。今回も歩き始めから高く伸びたトリプルクラウンの鼻をへし折られ、彼のトレイルには欠かせない旧友マタドールとのサプライズパーティに興じつつ、ロングディスタンストレイルの持つ底知れぬ磁力に引きずられるように歩みを進めていきます。
ぜひまたスケッチの旅にお付き合いください。
ロングトレイルが持つ磁力
テントの幕を雨が激しく叩く音で目を覚ました。暗闇の中、枕元に置いてあったiPhoneを拾い上げて画面を点灯させると、その明るさに目が眩む。
夜中の3時。シャツの上にダウンジャケットを着ているがそれでも寒い。僕は寝袋の中にすっぽりと頭まで潜り込む。グッと目を閉じて体のどこかに眠気の感覚がないか探すが、すでに覚醒してしまったようで、諦めて寝袋の中で地図アプリケーションを立ち上げて現在滞在しているアリゾナ州パタゴニアにあるテラソル・テントサイトの位置を確認した。

貧相なレインウェアのハイカーたち。アリゾナの砂漠をこれだけで乗り切れるかどうか、それはまだ誰にもわからない
パタゴニアはアリゾナトレイルを歩き始めたメキシコ国境からは50マイル(80km)進んだ地点に位置する小さな田舎町で、ここまでは3日かけて歩いて来た。
地図上でピンチインとピンチアウトを繰り返してトレイルの全体像を把握する。それからアメリカ全土、そして日本が見えるまでに縮小してみる。それを見ていると「やっとアメリカに戻って来れたのだ」と感慨深い気持ちになった。
実は2020年に僕はパタゴニア付近まで来たことがあった。その年の3月に渡米した僕はアメリカ人ハイカーのマタドール、スモフ、マーマンとチームを組んで、グランドキャニオンを3カ月あまりで縦走するヘイデュークトレイルをスルーハイキング(ワンシーズンに全セクションを歩き通すこと)するためにクルマでアリゾナを訪れた。

2020年にヘイデュークトレイルを目指す僕ら。マタドール、スモフ、マーマンとは2015年のパシフィック・クレスト・トレイルで出会った
彼らとは2015年のパシフィック・クレスト・トレイルで出会っていて、ことマタドールに関しては僕がアメリカに行くたびに共に過ごす親友だった。僕らは壮大なトレイルに心躍らせてクルマを走らせたのだったが、当時の大統領ドナルド・トランプから「パンデミック」という言葉が発せられた瞬間から、アメリカの状況が一変した。それはまるでテレビのチャンネルをコメディ番組からホラー映画に切り替えたの如く、突然で劇的な変化だった。
食料品店から日用品が姿を消し、レストランはマクドナルドでさえ閉じた。僕らは残された缶詰やチーズをひもじく食べることしかできなくなった。そして最終的に都市がロックダウンし始めたのだ。

都市封鎖時のラスベガス。路上には麻薬の売人とホームレスしかいなかった
行き場を失った僕らはユタ州のアーチーズ国立公園でキャンプや短いハイキングをして過ごしていたが、そのキャンプ地でバリケードを作って暴動に備える変人が現れ始めたりと、事態は混沌とした様相が増すばかりで、ついに、僕らは旅は諦めて解散することにした。

ダイナミックなアーチス国立公園をハイキングする
しかし、僕はせっかくのアメリカでのハイキングを諦めきれずに、隣の州のアリゾナトレイルを歩くべく長距離バスを乗り継いでメキシコ国境へ向かったのだが、途中の街で完全にバスが停止して行き場を失った。それが今滞在しているパタゴニアの近くだった。
バスカウンターが閉じられてチケットが買えないので、走行しているバスを立ち往生している人たちと一緒に停車させて、無理やり乗り込んだ。ちょうどその日が僕の誕生日3月22日だったので、僕はなんとも言えない虚しさを抱えながらバスで小さく丸まっていた。そしてフェニックス空港から逃げるようにして帰国したのだった。
帰国後はさらに強まるコロナウイルスによる混乱で、次第に海外トレイルに行くこと自体が億劫になって、日本で可能なアクティビティを探し始め、バイクパッキングやフライフィッシングにのめり込むようになった。それなりに楽しい日々を過ごしていたはずであったが、どこか喪失感が常に心の中にあり、地に足がつかない日々を送っていた。

アメリカから帰国して、すぐに購入した自転車、コナ・ユニットXでの旅にはまる
ある日から本来の自分をアメリカに置いてきてしまったような感覚が脳裏から離れなくなった。何よりも、年齢を重ねるごとに色々と複雑になっていく面倒臭いあらゆる責務や問題を、一度かなぐり捨てて日本から消え去りたかった。

ただアメリカのウィルダネスを放浪するだけで、何の生産性も無い旅が僕は途轍もなく好きなのだ。
こうして2年の月日を経て、僕はロングディスタンストレイルがもつ不思議な磁力に引き寄せられるように、またしてもアメリカに舞い戻って来てしまったのだった。
我はトリプルクラウナー様なり!

昨日の冷たい雨を取り返すような、暖かい日差しが降り注ぐテラソルのテントサイト
いつの間にか眠りに落ちていたようで、再び目を覚ますと体が汗ばんでいた。テント外に出るとアリゾナの強い日差しが降り注ぐ。僕はテラソルの広いキャンプサイトを横切り、オーナーの住居兼管理室がある建物の外に設置された子供用スペースでマグカップに水を充して飲む。キャンプ場にはアリゾナトレイルを行くハイカーとバイクパッカー達がのんびりと日光を浴びてくつろいでいた。

アリゾナトレイルを走るバイクパッカーたち。ハイカートラッシュ(注:長旅で乞食のような見た目になったロングディスタンストレイルハイカーのこと)の僕にはとてもお洒落に見えた

アメリカのバイクパッキング装備に興味津々だったので、次々と話しかけ自転車の写真を撮った
アリゾナトレイルはその多くがハイキングトレイルと自転車トレイルが共有されている。これまで歩いたトレイルはハイカーとバイカーは明確にトレイルが分けられていることが大半だったため、この形態は僕にとってとても新鮮で、2年ほど前からバイクパッキングにのめり込んでいる身としては、長距離オフロードを走るバイクパッカーたちとの出会いは興味をそそられるものがあった。
テントに戻ろうと歩き始めた瞬間、足の裏がズキりと痛んだ。きっと昨日、雨に降られまいと急いでトレイルを駆けたからだろう。雨でずぶ濡れにはならなかったが、その代償はあったようだ。
その時、僕の調子はお世辞にも良いとは言えなかった。その原因は明白で、完全にアリゾナトレイルを舐めていたからだ。

2017年に3大トレイルで最も難しいとされるコンチネンタル・ディバイド・トレイルを歩いてから、他のトレイルは簡単すぎるのではないかと思うことが増えてきた
アメリカ3大トレイルを制覇したトリプルクラウナー、つまり僕にとって、アリゾナトレイルは食後のデザートのようなものであると思っていた。これまでハイクしてきた4000km前後のロングディスタンストレイルと比べアリゾナトレイルは800マイル(1480km)なのでかなり短い。よって、全セクションを駆け抜けないと冬が訪れて雪が降り始めてしまうといったシビアなデッドラインが存在しない。
さらに砂漠が多いので気温が高く、雨に降られることも少ない。そしてトレイルが平坦なセクションも多い。だから、アリゾナトレイルは防寒装備は少なめに、バックパックのウェイトを軽くして高速で歩くことができる。
これまであまり軽量化を意識して来なかった僕だったが、小さなバックパックでトレイルを颯爽と駆けるウルトラライトなハイカーにずっと憧れを持っていた。僕はこれを機にウルトラライト化に挑戦してみようと考え、これまで60Lのバックパックを使用していたのに対し、今回はゴッサマーギアのクモ(36L)を使用していた。

アリゾナトレイルで使用したゴッサマーギアのクモ。これまでに比べてかなり軽量化したが、細かいウェイトには興味がないので、重さを測ることはしなかった。
そして、何よりもパシフィッククレストトレイル(以下PCT)、コンチネンタルディバイドトレイル(以下CDT)、アパラチアントレイル(以下AT)と既に3大トレイルを制覇していることが大きな自信となり、「我は王者なり! この程度のトレイルなど踏破できて至極当然である!」と感じずにはいられなかった。
アリゾナトレイルの最南端ターミナスはメキシコ国境にあり、メキシコ側はずっと果てまで続く荒野で、アメリカとメキシコを隔てるその境界は西側からずっと高く聳える鉄の壁が続いているのだが、スタート地点少し手前から貧相な有刺鉄線に変わり、僕は簡単にメキシコ側に入ることができた。

アリゾナトレイルのターミナスは国境を越えたメキシコ側にあったが、僕と見送りに来てくれた親友のマタドールは堂々と国境の有刺鉄線を潜り抜けて記念写真を撮った。
平地が続くメキシコ側とは対照的にアメリカ側はスタート直後から標高1800mから2800mまでの急な登りが始まる。どんどんと高度を上げメキシコ側を見渡すと、ただどこまでも荒野が続いていることが確認できただけだった。

山頂から見た平坦なメキシコの砂漠
そんなふうに意気揚々と歩き始めたのだが、初日から想定外の事態に直面した。自分の歩くスピードが途轍もなく遅いのだ。それはもう目も当てらないくらいに。
歩き始めこそ調子が良かったが、すぐに体が重く感じ始め、徐々にゆっくりとしか歩くことができなくなった。その日の目的地である水場に到着した頃には想定の3時間遅れの19時を過ぎていて、すでに辺りは暗くなっていた。

アリゾナトレイルで最初の「水場」は、バスタブに溜められた水だった。ハイカーはこれを濾過して飲む
僕は自分の歩く速度の遅さに戸惑った。どこか体の調子が悪いのではなかろうか? そう思ったりもしたが、よく考えると海外トレイルを歩くのは3年ぶりで、その時に歩いたアパラチアントレイルと同じように歩ける感覚でいるのがそもそも間違っていたのだ。3年のブランクは大きく、また一から体を作って慣れていくしかないのだろう。
マイ・ハイキング・バディ
テラソルのキャンプサイトでは、親友で昨年のヘイデュークトレイル未遂事件でも一緒だったマタドールと合流することになっていた。彼はアリゾナの友人の結婚式に参加するので、その前に数日間僕とハイキングする予定だ。

アトランタからアリゾナまで運転中、木の皮で作ったゴーグルを着用するマタドール
今回の旅で彼には既に世話になっていた。東海岸のジョージア州アトランタの実家で僕を数日泊めてくれた後に、はるばるアリゾナトレイルまでクルマで4日かけて送り届けてくれたのだ。その後、彼はこの先のセクションまでクルマを移動して停車し、積んであったオフロードバイクでこちらに向かっている。そして僕と停車場所まで一緒にハイキングをした後、またパタゴニアまでクルマで移動してからバイクをピックアップする手筈らしい。何とも面倒臭いことをする男だが、その柔軟な行動力に僕はこれまで何度も助けられている。
マタドールが到着したのは15時ごろだった。

バイクでパタゴニアに到着したマタドール
「よう、スケッチ! 調子はどうだい?」
「何だかとても歩くのが遅くなってるよ。」
「本当? お前はかなりストロングハイカーな筈だけどな。」
「多分、久しぶりだからかな? そう思いたいね。」
「すぐに元に戻るさ。何たって俺たちはトリプルクラウナーだぜ。」
彼はバイクに括り付けていたパランテの小さなバックパックをヒョイと担ぐと「さあ、ハイキングしようぜ」と言った。マタドールにとってアリゾナトレイルは既に知り尽くしているトレイルだった。なぜなら彼は既に3度もこのトレイルを踏破していて、最後のハイキングでは当時のFKT(Fastest Known Time=最速記録)を打ち立てている。
キャンプサイトを後にしてパタゴニアの町にある小さなローカルマーケットで5日分の食料を購入してバックパックに詰める。それが終わると乾いた草原を切り裂くように伸びるダートロードをふたりで黙々と歩き始めた。

なだらかな勾配のダートロードを黙々と歩く
昨日の雨と打って変わっての晴天で気温もかなり高い。しばらく歩いていると、ピックアップトラックが僕らの横に停まった。
「君らハイカーだろ? この先まで送ってやろうか?」
「俺らは大丈夫です。ありがとう。」
僕らは何故そんなことを言われるのか不思議でならなかったが、その助手席で若い女性ハイカーが気まずそうにこちらを見ているのに気がついて苦笑いをする。
「気をつけてな。夜は冷えるぞ。」
そう言うと、ピックアップトラックは鈍いエンジン音を響かせて土埃を巻き上げながら去っていった。
「彼女はなんで自分で歩かないのだろう?」
「知るかよそんなこと。まぁいろんなハイカーがいるって事だろうよ。」
僕らは再びダートロードを黙々と歩き続けた。この日も足の裏は痛んでいたが、本来のペースに近い速度でハイキングを続けていた。これにはマタドールも安心したようだった。
その日は陽が暮れるまで歩かずに、牛の糞が転がるトレイルヘッドの駐車スペースにテントを張り、ふたりでのんびりと話をしながら夕食を取る。そして各々テントの中でネットフリックスの動画を見て過ごした。

朝にコーヒーを淹れるマタドール。もちろんインスタントコーヒーだ
朝にテントから出るとマタドールは既に起きていて、僕に気がつくと「おはようスケッチ。コーヒー飲むかい?」と言った。彼は家でもトレイルでもいつも朝にコーヒーを淹れてくれる。インスタントのコーヒーを啜りながら、僕らは次の水場の場所を確認する。アリゾナトレイルは乾燥地帯を歩くので水場の把握と持ち運ぶ量の見極めが大切だ。
「次の水場の湧水があるポイントまではかなり遠いと思うけど、水が足りるか不安だな。」
「確かにベアスプリングは遠いけど、おそらく次のトレイルヘッドにウォーターキャッシュ(注:ハイカーの補給用に置かれた水のタンク)があるはずだ。」
「何でそんなこと知ってるんだよ。」
「ファーアウトのコメントに書いてあったからさ。アリゾナトレイルのウォーターキャッシュの場所はコメントをチェックした方が良いぞ。」
地図アプリケーションのファーアウトには地形図やルート以外に、トレイルヘッドやテント場などの場所も表示され、そのチェックポイントごとにハイカーが自由にコメントを書き込めるようになっている。これまでは水場の状況を確認する程度にしか活用していなかったが、アリゾナトレイルでは細かくチェックしないとウォーターキャッシュの場所を知ることができないのだ。
ファーアウトを開いてこれから行くトレイルヘッドのコメントを読むと、誰かが昨日の夕方に10リットルほどの水が置いてあったと書き込んでいた。アリゾナトレイルを歩くハイカーの量と事前に確認したレジスター(入山届の様なものだが、普通のノートが置かれていて名前を書くだけの場合も多い)からして、僕らとそのトレイルヘッドの間には多く見積もっても3人ほどしかいないように思える。つまり、まだ水は十分にあるだろう。

歩く速度が速いマタドールは水場でのんびりと僕の到着を待つ
「地図アプリケーションはゲームチェンジャーだぜ。こいつのおかげでハイキングはとても簡単になった。」
マタドールが言う。僕もまさしく同意であり、もはやこれがないとハイキングを不自由に感じるほど依存してしまっている。加えてこの数年で通信会社のエリア拡大により標高の高いところに行けば大体通信が可能になっているので、便利さはどんどん増している。
サプライズパーティ

のんびりとダートロードを歩く。日差しがとても強い。
昨日と変わらず起伏の少ないダートロードが続いていた。大地は乾燥していて黄金色の背の低い草が覆っている。そしてまばらに4〜5メートルほどの木々がポツポツと生えている。そして遠方の丘にはゴツゴツとした岩壁がかさぶたのようにところどころに飛び出していた。アリゾナという場所は砂地にサボテンが生えているような場所だと思っていたが、どうやら違うようだ。
トレイルは良い意味で退屈だった。気温は高く乾燥している。半袖シャツとショーツ、そして帽子を深く被ってサングラスをすれば身軽にどこまでも歩けそうだ。
スルーハイクにおいて、唯一と言って良い共通の価値観が「距離」だ。ハイカーによってトレイルに対して求めるものは違うが、この距離という尺度はロング・ディスタンス・トレイルをスルーハイクするためには共通だ。だから歩くスピードが早く、そして距離を伸ばせるハイカーはある種の制約から解き放たれて自由になれる。それはトレイル上において、実社会でいう「裕福」に近い感覚だと僕は思う。
そんな1ドルの利益も生まない考察をしているうちに、気がつけばマタドールの姿が遥か彼方で小さな点となっていた。彼のスピードには到底追いつけないので、歩く速度を変えなかった。それに、次第に足の裏にヒリヒリとした痛みを感じ始めていたので、悪化させたくはなかった。

トレイルヘッドの岩の裏に水が入ったボトルを発見
「ほら、やっぱり水はあっただろう。」
僕が遅れてトレイルヘッドに到着するとマタドールは水が入ったボトルをこちらに掲げて、満足そうに言った。
駆け寄ってみると、3リットルほどのボトルが10本あり、そのうち5本はまだ水が満タンだ。アリゾナトレイルは水の補給が困難だと聞いていたが、情報をうまく入手さえすれば意外にも問題ないのかもしれない。濾過なしで飲める貴重な水なので可能な限り持ち運びたいと思ったが、この先のベアスプリングも名前からして湧水なので、状態は良さそうだ。ここから3時間ほどの距離なので、2リットルだけ持ち運ぶことにして、すぐにその場を後にした。

キャンプ用チェアを出して僕を待つマタドールとハイカーたち
この日のマタドールはやけに歩くのが速い。休憩ポイントで合流し、また歩き始めたらすぐに彼はものすごい速さで歩き始め見えなくなる。その繰り返しだ。
午後の16時ごろにアリゾナトレイルがダートロードと交わる箇所になってその理由が分かった。僕が到着するとマタドールは自分のバンの横にキャンプ用チェアを並べて、そのひとつに座りビールを用意して待っていた。彼は僕にトレイルマジックをしたくて急いでいたのだ。
「マタドール! 最高のトレイルマジックじゃないか!」
「そう思うかい。とりあえず座れよ。ビールとソーダ、あと俺のママ特製のクッキーもあるぜ。」
「とりあえずビールだ。まずはそこからだ。」
僕は手渡されたビールのプルタブを抜いた。
「乾杯! そしてありがとう!」
缶からは泡が溢れ出し、それを啜る。ハイキング直後のビールは苦く、喉を痺れさせた。
ふたりでビールを飲んでいるとハイカーが訪れ、足を止めてトレイルマジックを嬉しそうに受けていた。次第にひとりふたりと人数が増え、最終的には4人のハイカーが腰を据えてビールを飲み始めた。彼らがこの場所でテント泊をするのは明白だ。
だいぶん酔いが回りはじめた僕は、淡い青色が広がる空をぼんやりと眺めていた。
「誕生日おめでとう!」
その声に反応して視線を下げると、マタドールが火の灯ったロウソクをのせた小さなケーキを持って、こちらに歩み寄ってきた。間違いなく僕の方を見ている。他のハイカーは拍手をして僕の名前を叫ぶ。これはサプライズバースデーパーティだ。

バースディーケーキを用意してくれたマタドール
僕は誕生日を祝われたことにとても驚いた。なんたってその日は3月21日。僕の誕生日は翌日なのだ。僕は笑顔を作って彼らの顔を見て、その雰囲気から計画的に1日早く祝われた誕生日ではなく、単純に僕の誕生日を間違えているのだと察した。
「本当に嬉しい! 本当だ! みんなありがとう!」
僕はとりあえず叫んだ。実際に祝ってくれること自体はとても幸福なことだ。皆は声を合わせてバースデーソングを歌う。
「なあ。どんな気分だ? 36歳になったんだよな!」
「そうだな。まだ35歳みたいな気分だよ。」
バースデーパーティは大いに盛り上がり、その日は暗くなるまで飲み続けた。最後は疲れ果ててテントの中で気絶した様に眠った。

砂に書かれたバースデーメッセージ
翌日、僕は喉の渇きで目を覚ます。幾分まだ酒が残っているようで、全ての感覚が鈍い。次第に尿意が強くなってきたので、テントから出るとマタドールは焚き火をして暖を取っていた。僕は少し歩いて茂みへ行って用を足していた。朝日で赤く燃えている遠くの山を見ていると、その方角から温かく強い風が吹いた。まるで世界が深く呼吸をして目を覚ましたようだ。
その瞬間、僕は昨日よりひとつ歳を重ねた事を強く意識した。明確に「歳をとった」と自覚したのは人生で初めての事だった。これが36という数字ゆえなのか、はたまたトレイル上で誕生日を迎えたからなのか分からなかったが奇妙な感覚だ。

焚き火は常に離れ難いもの。ハイカーたちはのんびりと過ごしていた
僕は焚き火の方へ足を進め、チェアに座る。僕はまだその正体の掴めない気持ちを心に留めながら、揺れる火をぼんやりと眺めていると、そんな僕にマタドールがマグカップに入ったコーヒーを差し出した。昨日と変わらない安いインスタントコーヒーの味だ。ふとマタドールの顔を見て少しだけ奇妙な感覚が分かったような気がした。
僕、いや僕らは、もうロング・ディスタンス・ハイキングという世界が人生と深く絡み合い始めて、抜け出すことはできなくなっているということだ。それはまるでコーヒーと同じように習慣になっているということだろうか。いや、もはや依存とも言えるのではないだろうか。
どこか取り返しのつかないところまで来てしまった気がした。まだアリゾナトレイルは始まったばかりだというのに。

マタドールとはここでお別れ。またすぐに再会するとお互い思っているので寂しくはない
【#2に続く】