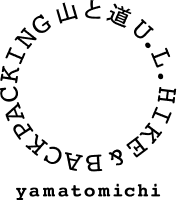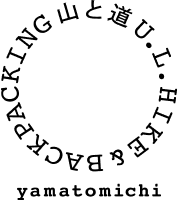「キルギス」という国名を聞いて、何を想像されますか? シルクロード? 大草原? 遊牧の暮らし? まあ、そんなことを連想できれば良い方で、多くの日本人にとってはイメージの糸口さえ掴めないかもしれません。
中国、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンに囲まれた中央アジアに位置し、国土の大部分を天山(テンシャン)山脈が占めるキルギスは、これから始まる本稿の写真を見ていただければわかる通り、実は言葉を失うほどの絶景で溢れた山岳国家。そんなキルギスの天山山脈を途中中断を挟みつつ4ヶ月、1000km以上に渡って歩いたハイキングの記憶を、読者の安原あかねさんがその澄み切った空気まで写り込んだような美しい写真とリリカルなテキストで素敵な投稿にまとめてくれました。
人々の顔つきこそ日本人とそっくりなものの、地理的にも文化的にも、あらゆる意味で日本とは遠くかけ離れた国、キルギス。そんな人の住む世界の境界のような土地へ、しばし思いを馳せてみませんか?
山と道JOURNALSでは読者からの旅の記録の投稿を随時お待ちしております。ロングトレイルからデイハイクまで旅の大小は問いませんので、まずはご連絡ください。
砂降るトラックと低い雲
揺れるたび砂が降って来るトラックに乗せてもらってから、帰りたくて仕方がなかった。
後ろを振り向くたび、荷台の馬と目が合う。川沿いの、今にも崩れ落ちそうな、道ともいえぬ砂地をぐんぐん進む。
「ここがEchkili-tashだ。」
クルマを3台乗り継いで辿り着いた先は、村ですらなかった。ユルタという遊牧民のテントが1軒、ポツンと佇んでいるだけだ。トラックを降りたものの、去っていくのを見届けるのが辛いほど、心細かった。

トラックからの景色。この地点では草が青い。
ここからは、15日間歩くしか帰る手段がない。両手に大きな不安を抱えたまま、どんどん小さくなるトラックを見送った。この時点で標高は3000mを越えている。背が縮みそうなほど荷物が重い。加えて、空は分厚い雲に覆われている。
不安を紛らわすため、アニマルクラッカーを食べた。キルギスらしく、羊だけが忠実に再現されている。お腹が満たされると、不安も少し和らいだ。
バスに忘れ物をしたり、乗せてもらった車が故障したりして、朝から何も食べていなかったことに気付く。8時に町を出発して、もう16時を過ぎようとしている…。早くテントを張らないと、陽が暮れてしまう。

キルギスのアニマルクラッカー。ひつじに比べてカメとゾウのクオリティが低い。

標高3000m地点。100頭ぐらいの羊を放牧している。
このとき、私たちはキルギスの天山山脈を2600km歩く計画のもと歩いていた。8日から15日ほど山を歩いては、町に戻り食料とエネルギーを補給してまた山に行く…その繰り返しだ。
これまで、バルカン半島やトルコ、ジョージアなど、世界の様々なトレイルを歩いてきた。お湯を沸かすのにどれほど時間がかかり、どれだけの燃料や水を必要とし、どれほどゴミを排出するか…全てが可視化される山歩きに、私たちは魅了されてしまった。
さらに、世界にはまだ、歩いてしか行けない場所での暮らしがわずかに残っているということを、山を歩き始めてから知った。そこでの暮らしは、自然と人間の力が対等にある。最後の余白のような暮らしを知るためにも、山と暮らしが近い国を選んで歩いていた。中央アジアに位置するキルギスタンはかつての遊牧国家で、夏になると家畜と共に山で過ごす半定住生活を営む人が今でも存在する。
彼が自作したテントや食糧を背負って、川をじゃぶじゃぶ渉ったり、氷河を歩いたりしてきた。時には石積みの家に招かれて羊を捌いてもらったり、泊まらせてもらったりしながら、なんとかここまでやってきた。途中体調不良による1ヶ月程の中断を挟みつつ、このセクションを終えたら1200kmに達する。5月から歩きはじめ、もう8月下旬に差し掛かっている。

別セクションにて:6月になると小麦粉やじゃがいもを馬に積んで、家畜と共に夏の拠点に向かう。誰も住まなくなった石積みの家は山小屋のような役割を果たしていて、このような小屋を転々としながら3日くらいかけて本拠地(作りは同様)に向かう。

別セクションにて:この前日に羊を絞めてクルダックというキルギスの郷土料理を振る舞ってくれた。

別セクションにて:この日、ここに集まったのは計9人。小屋に入りきれず、標高2900mの雪の中テントもタープもないまま外で寝ていた。
歩いていると、雨が降り始めてきた。次第に雨足は強まり、靴が中までぐっしょりと濡れた。手足は凍えるほど冷たい。2時間ほど降り続いた雨は、18時を過ぎた頃にぴたりと止み、灰色の雲の隙間から光が差した。
8月の黄金色の大地は、白い光を帯びて神々しいほどに輝いていた。木も動物もいないこの地では、雨が止んでも鳥すら鳴かない。ただひたすら、静かだった。

2021年8月19日18:43:雨上がりの標高3000m地点にて。
この夜は、小高い丘の麓にテントを張ることにした。テントを張ってから、ぐっしょり濡れた靴下や服を替えた。着替えて温かいスープを飲んでも冷え切った体が暖まることはなく、寝袋の中に潜り込んだが、その夜はこの旅で初めて寒くて眠れなかった。
翌朝起きてみると、トレッキングポールは見事に凍っていた。寒すぎて寝袋から出られないでいるわたしをよそに、彼はせっせとパッキングを始めた。
「寒いときは歩くしかないんだよ。」
渋々寝袋から出て、のろのろとパッキングを始めた。ふと目をやると、凍った真っ白な大地が朝日を浴びて輝いていた。もやの向こうに、うっすらと山脈が見える。
山にいることに慣れてしまうと、こうした特別な瞬間を見逃してしまいがちだ。次いつ訪れるかすら分からないこの場所で、その景色をしっかりと目に焼き付ける。

2021年8月20日9:25。全長60kmの氷河の融解水から成る川。中国のタリム盆地まで続く。
この日、ユルタを2軒見かけた。こんな人里離れた場所でも、人々は長らく生活してきたようだ。町から遠く、種を撒いても芽が出ない。川から水を汲み、乾いた牛糞を燃料に火を熾し、どこまでも馬で移動する…。そんな場所で暮らす彼らは、資本主義の世界で暮らす私たちとは全く異なる種類の便利さを見出しているように感じる。
うち1軒のドアをノックし、少量の油を譲ってもらった。ここに来るまでに何台もクルマを乗り継ぐ間に、どこかに置いてきてしまったのだ。彼らはお金は受け取らないので、引き換えにチョコレートとドライフルーツを渡す。子供達は珍しい訪問者にキャッキャしていた。

5歳くらいの子供がロバに乗ってひとりで羊の群れを誘導していた。ペットボトルに入れた母ロバのミルクを子供のロバに与えるシーン。
アイベックスの気持ちになってみたかったんだ
歩き始めてから3日が経過した。距離にして58km。総距離の5分の1を歩き終えたところだ。地図上は平坦だった道は実際には凹凸が多く、予想以上に時間がかかった。点と点を繋ぐような私たちのトレイルは、予測ができない。地図上で平坦な道も、茨の道だったりする。この日、目指してやってきた湖は枯れていた。
日が暮れる前にテントを張ってから、明日渡る予定の川を確認しに向かった。太陽の熱で氷河が溶け出し、午後になると水量が増す。夕暮れ前の増水した川は、まるで灰色の生き物のように轟音を立ててうごめいていて、いつも飲み込まれそうで不安になる。
翌朝になると案の定、灰色の生き物はどこかへ行ってしまったかのように川は穏やかだった。
「水を読むんだ。」
いつも言われる言葉。幼少期からカヤックをし、川で泳いで育った彼は、水と親しい。一方、幼い頃からシャワーも嫌いで、プールの授業をいつもズル休みしてきた私は、水が怖い。どんなに澄んだ川でも、身構えてしまう。
澄んでいると言えど、この川も流れはそれなりに強く、早朝の氷河の融解水は凍るほど冷たい。彼の膝上あたりだと、私の太ももの付け根あたりの水位だ。一歩一歩、ポールで探りながら、滑らないように、踏み外さないように渡る。
渡り切った頃には、一仕事を終えた後のような疲労感と安堵、そしてかじかんだ脚は真っ赤で、今にもポキンと折れてしまいそうだ。

文中に出てきたのとは違うアイベックスの角。彼が担いだものはさらに大きく、3kgぐらいあったそう。
その日、川を渉り終えると、何やら異様な臭いが漂ってきた。
「今日はずいぶん快便だったんじゃない?」
「違うんだ! 近付かないほうがいい!」
「どうしたの?」
「アイベックスの気持ちになってみたいと思ったんだ。どれくらいの重さのそれを頭にのせて生きてきたのか…この角を頭の上に持ち上げて、君の名前を呼ぼうとしたとき、中から液体が垂れてきたんだよ…つまり、腐った脳みそ…」
彼のそばに、80cmはありそうな野生のアイベックスの角が転がっていた。彼に降りかかったその強烈な死臭は、2m先からでも漂ってきた。
バックパック、フリース、インナー、全てを脱いで川で洗った。
「死臭が取れない…。もうだめだ、町に帰りたい。好きなだけビール飲んで映画観てベッドで寝たい。こんな死臭を纏って、10日以上歩くのはごめんだ。」
着替えのない彼は全裸のまま大地に突っ伏した。
「今日は歩くのやめようか。どっちにしても、乾くのを待ってから峠を越えるのは危ないし、楽しめないし。」
幸い、その日はよく晴れて日差しが強かった。河原から少し進んだ先にテントを張って濡れた服を広げ、ゼロデイを迎えた。




新雪を心配していたが、雪はなかった。ストレスもなくただ楽しかった氷河ウォーク。峠を越えた先に見えるのはイニリチェク渓谷。
果てしなく遠いキルギス最高峰
数日間、わたしたちはとにかく歩き続けた。氷河を渉り、4200mの峠を越えた先には、壮大な景色が広がっていた。眼下に広がるは、全長62kmの氷河からの融解水から成るイニリチェク川。遠くに聳え立つは天山山脈最高峰のポベーダ山。ここから川に沿って歩き、氷河を50km歩いて標高4800mのビューポイントを目指す予定だ。
川の先端まで辿り着き、長い長いモレーン(氷河が削り取った岩石・岩屑や土砂などが土手のように堆積した地形)ウォークが始まった。足場の悪い巨大な岩を上ったり下りたりして、1時間が経った。遠くに聳え立つポベーダ山は果てしなく遠いままだ。ふと不安になって地図を確認してみると、なんと1時間で1kmしか進んでいない。
ポベーダ山を見つめながら考える。
「帰ろうか。」
意見は一致した。安全面を第一に考慮した結果だけど、それだけではない…満たされたのだ。
これまで、何かを追い求めるかのように歩いてきた。距離の目標はあくまで目安でしかなく、私たちはいつもそれを達成しなくても「ある地点」に到達したら歩くのをやめてきた。「ある地点」とは、物理的な地点ではなく、精神的に満たされた時にしか見えない蜃気楼のようなもの。そこに到達した瞬間、そこにあるすべては過去のものに思えて、まだ見ぬ景色への憧れや未練が薄れていく。
巨大な岩の上に腰をかけ、朝食の準備をした。最後まで遠いままのキルギス最高峰を見つめながらグラノーラを無心で食べた。


イニリチェク渓谷へ向かう。肝心のポベーダ山は1枚も収めていなかった。
帰ると言ってもここから麓の村まで歩いていて4日はかかる。この美しい景色との別れが名残惜しくて、後ろ向きに歩いた。
私達は歩いてる間ほとんど会話をしないが、この日は珍しく彼がこう切り出した。
「ユルタを買って、ひつじとヤギと一緒に1年ぐらい山で暮らしてみようか。」
「で、ひつじは最後に食べるの?」
「食べない。ひつじと暮らすという体験をするだけ。」
「ロバもいいな。ロバのミルクはレチノールが豊富で、美肌効果があるんだって。」
「荷物の運搬もやってもらうの?」
「あんまり重いと可哀想だよね。」
*
*
*
こうして私はいま東京にいる。山で木の実を採集したり枝を集めて火を起こしたりした結果、蛇口を捻れば水が出て、新月の夜でもなにひとつ不自由なく料理ができる暮らしを謳歌している。ロバとヤギへの憧れを秘めながら。

標高3700m:雨上がりの18:44。テントからの景色。