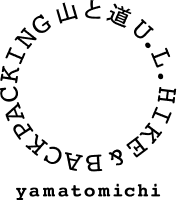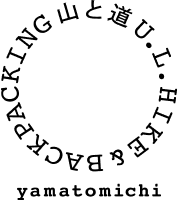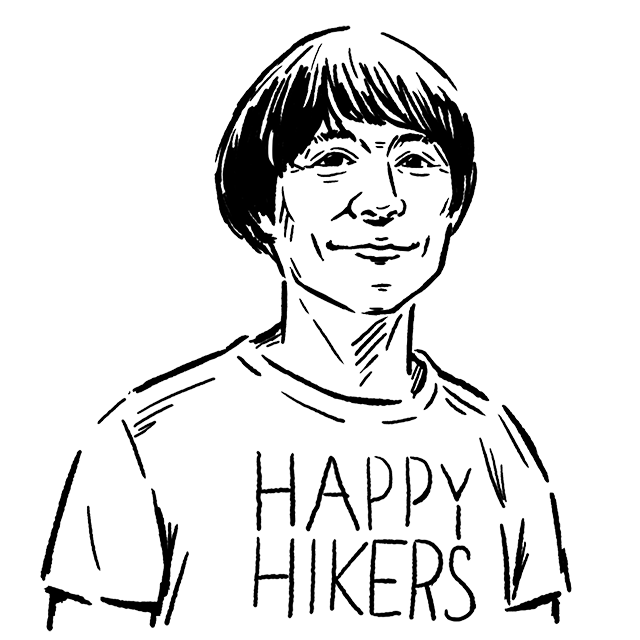INTRODUCTION
2017年の6月から10月にかけて、山と道は現代美術のフィールドを中心に幅広い活動を行う豊嶋秀樹と共に、トークイベントとポップアップショップを組み合わせて日本中を駆け巡るツアー『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を行いました。
北は北海道から南は鹿児島まで、毎回その土地に所縁のあるゲストスピーカーをお迎えしてお話しを伺い、地元のハイカーやお客様と交流した『HIKE / LIFE / COMMUNITY』とは、いったい何だったのか? この『HIKE / LIFE / COMMUNITY TOUR 2017 REMINISCENCE(=回想録)』で、各会場のゲストスピーカーの方々に豊嶋秀樹が収録していたインタビューを通じて振り返っていきます。
#16となる今回は、九州と山口の山を対象とした山雑誌「季刊のぼろ」創刊時より編集に携わってきたフリーライター米村奈穂さんと山の話です。
山岳部の顧問をしていた父親に幼い頃から連れられ山に入っていたという米村さん。その後、どのように山と関わることになるのか? 山との出会いは人それぞれあると思うが、、、それは必然なのかもしれません。

ドアが開いた

撮影:吉田美湖
九州が比較的大きな島だということは、なじみのない人には想像しにくいだろう。僕も実際に住むまではピンとこなかった。
鹿児島から福岡への移動は、ほぼ真北に300km近くになるので、風土もずいぶん変わってくる。そして何より、福岡は日本海側に面した都市なので、気候は日本海側の影響を受けることになる。九州は南国で年中暖かいというイメージを抱く人も多いだろうが、福岡にそれは当たらない。冬にはそれがはっきりとわかる。福岡の冬は、北海道から、東北、北陸、山陰と続く、どんよりと暗く陰鬱な日本海側特有のそれだ。降るのは雪ではなく雨なのだが、冬の湿度の高さが、僕には昔住んだロンドンを思わせる。
とはいえ、季節はまだ10月の頭で、南国と言われても仕方ないくらいの陽射しがサンサンと降りそそいでいる。夏が秋に持ち場をあけ渡すのを拒んでいるかのようだ。
今夜のHLCのイベントは僕の住む福岡での開催となる。
トークのゲストは、九州の山に興味のある人ならおそらく誰でも知っている雑誌、「季刊のぼろ」の米村奈穂さんだ。「季刊のぼろ」は、西日本新聞が発行する九州と山口の山を扱う雑誌で、米村さんは、創刊から5年間(2017年取材当時)にわたって編集を務めている。
「父が亡くなったときですね。まるでドアが開いたようでした」
山に登るようになったきっかけをたずねると、米村さんはきっぱりとそう答えた。
「父は、私が26歳のときに急に亡くなりました。お葬式も終わってすこし落ち着いたころに、私の友人が来てくれ、父の部屋を見て『お父さん、山好きだったんだね』ってボソっと言ったんです。私は父が山を好きだったということさえも忘れてしまっていました。でも、友人のひと言で、父との山のことを思い出して、連れられて行った山の話をたくさんしたんでしょうね。『じゃあ、山に行こうよ』と友人は言ってくれ、『くじゅう(九重連山。九州を代表する山脈)』に一緒に行ったんです。それが最初ですね」
米村さんと出会ったのは、僕が福岡に来てすぐのことだった。「くじゅう」に行こうと、福岡に引っ越した僕を夏目くんが訪ねてきたのに合わせて、小さなトークイベントを開催したことあった。米村さんはそのイベントに来てくれた。
小柄でニコニコとすこし大げさな身ぶりでひょうきんに話す、というと本人に異議申し立てされるかもしれないが、そんな米村さんの登山のきっかけが、父親の死だったということに僕は少なからず驚いた。人はそれぞれの理由で山に登り始めるのだ。
「父が亡くなってから、ショックだった私は仏壇に手を合わせられないくらいでした。手を合わせると父の死を認めてしまうような気がして。友人がそんな私を見かねたのか、『山に埋めてあげたらいいんじゃない?』って言いだしたんです。それで、土に還る粘土で入れ物を焼いて、その中に父の小さい骨をひとつ入れてよく一緒に登った山に持って行きました。登山道からは外れた、誰も行けないような山頂付近の崖っぷちの、自宅の方角を向いたところに骨を埋めてきました」
遺灰を海に撒くというような小説めいた話はよく聞くかもしれないが、実際に父親の遺骨を山に埋めにいったという話を聞いたのは初めてだった。
「私は、そのときの山登りが本当に楽しくて、自然に『次、どこに行こうか』って言っていました。『次は、屋久島行きたくない?』って。それから、どんどん山がおもしろくなっていって止められなくなってしまいました。友人たちはそんな私についていけないよという感じでしたけど」
米村さんは、いつものように大きな手ぶりで楽しそうに話した。

アルバイト募集
「屋久島から帰ってきた次の日に、もう抑えられないってなって思いました。でも、ひとりで盛り上がっているのが恥ずかしくて、この気持ちを人には言えなくてひた隠しにしてました」
本人は隠しているつもりでも、実際はぜんぜん隠しきれていなかったはずだ。
「ああ、これはもう止められないと思ってるところに、アウトドアメーカーのショップに『アルバイト募集』と貼ってあるのを見てすぐに電話したんですよ!」
米村さんは、『電話したんですよ!』のところで受話器を耳に当てて電話番号を大げさにプッシュするしぐさをした。それが時代を感じさせて、僕は思わず笑いだしてしまった。
「まだそのときは別の仕事をしていたんですが、受かるかどうかもわからなかったので、会社には内緒で面接に行ったんです。『いつから働けますか?』って面接の最後に言われて、急にどうしようって慌てました。本当にジェットコースターに乗っているみたいでした」
こうして次々と山のドアが開く前の米村さんは、福岡にある画材屋さんに勤めていた。「のぼろ」で編集者になるまでに短くはない道のりがあった。
「そこは、福岡にある老舗の画材屋さんで、へんてこなものばっかり売っているんですよ。年にひとつしか売れないものとか。なんでこんなものいるんだろうって思っていたら、『これは3年に1回、なんとかさんが使うから』って。本当に個人のためだけに置いている在庫なんですよ。でも『あの人には絶対に必要だから置いておかないといけない』とか。私はここですごくニッチな世界の専門的な分野で働くことの楽しさのようなものを経験しました。画材屋さんで働くのが楽しいのと同じように、自分が好きな山の道具を扱う店で働くのはもっと楽しいんじゃないかなって思ったんです」
米村さんは、その後、採用となったアウトドアメーカーのショップで10年近く働くことになった。「のぼろ」の話がなければきっとそのままそこで働いていただろうと振り返る。米村さんのこれまでの人生は、ゴールを設定してそこを目指してやるというよりも、その時やっていることが次のことを呼び、次のことがさらに先のことに繋がっているようだった。
山に行くスタイルは様々だが、その人なりの山との付き合い方は、多かれ少なかれ、何らかの影響を僕たちの生き方に与えている。それは、意識的であろうと無意識的であろうと、空気と呼吸のように切っても切れない関係を結んでいる。
米村さんの山もいろんな人生の方向を与えてくれているようだ。山やハイキングは、たとえメタファーとしてであっても、それをわかりやすいカタチで教えてくれる。人生は山あり、谷ありだ。

写真提供:米村奈穂
山よりおじさん
「山の何が好きなのかって聞かれたら、やっぱり山小屋が一番好き。登る行為自体よりも、むしろ山小屋に滞在したり、小屋を営んでる人たちの話を聞いたり、小屋にやってくる人たちと話をしたり。いちばん萌えるのは山小屋です」
米村さんは、そう言ってにっこりと笑った。
山では人に会いたくないというような方もたくさんいると思うが、山での出会いを楽しみにしている人も意外と多いと思う。日本の山にはたくさんの山小屋があって、山小屋はいつでも山旅の拠点や休憩のポイントとなってくれる。そして、山小屋には、たくさんのストーリーが付きもので、小屋主や小屋番さんの話を聞いているだけでも飽きることがない。
「よく行くのは、長崎と佐賀の県境の多良山系にある金泉寺山小屋と、くじゅうの法華院温泉山荘ですね。長者原からちょっとあがったところにある、九重ヒュッテにもよく行きます。あとは、祖母山九合目小屋(※1)。テクノ好きな管理人のおじさん。この前は夜通しでダフトパンクのPVとか見せられて」
楽しくて仕方ないという感じで米村さんの山小屋の話は止まらない。
僕自身は、もっぱらテント山行派なので、正直言うとあまり山小屋に泊まったことはないのだが、泊まった小屋のことは今でもよく覚えている。北アルプスを縦走している途中で嵐に見舞われて五竜山荘で停滞中に、暇つぶしに小屋にあった「山小屋大全」という雑誌で片っ端から山小屋情報をチェックして、泊まったこともほとんどないのにすっかり北アルプスの山小屋事情に詳しくなってしまった。
山小屋にもいろんなタイプがあって、みんなそれぞれに自分の気に入りがあるようだった。そして、それが山小屋ごとの文化を作っている。
「『のぼろ』に入る前の山登りは単独で行くことが多くて、そのことに陶酔していたような感じもありました。ひとりでできるんだってことに喜びを感じたりして。でも、仕事で山に入るとなると誰かと一緒に行かなくちゃいけないんですが、地元の方々や山岳会の協力を得たり、山小屋の人に話を聞いたりしているうちにそれがおもしろくなってきました。人と接することに積極的じゃなかった自分が、ガラっと変わりましたね。記事を作っていても、『米村さんが作ったってすぐわかるよ、おじさんが出てるから』って言われたりするくらい。山よりおじさんなんですかね」
そう言って、米村さんはまた楽しそうに笑った。
話を聞き終わって米村さんと別れた後、『のぼろ』の編集部のある西日本新聞社が入っている福岡のど真ん中にあるビルを見上げた。僕は『のぼろ』でエッセイを連載させてもらったりしたこともあったので、打ち合わせのためにここに米村さんを訪ねて行ったことがある。
別れ際に、「実は…」と言って、米村さんはもうしばらくで、『のぼろ』をやめることにしたと僕に告げた。やめてどうするのかと驚いて僕が聞くと、「全然考えてないです」と米村さんは答えた。もしかすると、色々と考えていることもあったのかもしれなかったが、僕はそれ以上聞くのはやめておいた。そう、人生は山あり、谷ありだ。
僕は、米村さんが『のぼろ』はこうありたいと言っていた話を思い出した。
「土地のものをそこで食べるとおいしいように、私たちの山をポリポリと、ここ九州でおいしく食べたい。そんな本になりたいです」
後日談を少し。というのも、インタビューのために米村さんに話を聞かせてもらってから、この原稿書くまでに1年以上たってしまっていたので、僕は、米村さんが『のぼろ』をやめてしまってからどうしているか気になっていた。
久しぶりに米村さんに電話をかけ、少しの世間話の後、今どうしているかたずねると、独立した実感もないままに、辞めてからも『のぼろ』のことも手伝いながら、なんとく九州の山のフリーライターという感じでやっていると少し決まり悪そうに答えた。大分県の耶馬溪の景勝地をめぐるガイドブックづくりに携わるなど、九州全体を見渡すというよりも、ある特定の場所について深く関わるようになっているという。
全国ではなく、九州。九州よりもっと小さな一ヶ所をより深く。米村さんは、それは『のぼろ』が教えてくれたことだと言った。
「あいかわらず、声をかけられたらそっちに行っちゃうんですよ」
楽しくやっているのか最後に聞くと、米村さんは「うん、楽しくやってますよ!」と元気に答えた。いつか、米村さんにどこかの山小屋に連れて行ってもらって、ゆっくり話したいなと僕は思った。
僕たちの旅のはなしに戻ろう。福岡で住めそうなくらい大きなハイエースを借りて、ここからは、夏目ファミリーや山と道スタッフとともに西日本編の旅を一緒に行くことになっていた。鹿児島からプロジェクトはすでに始まってはいたけれど、福岡に住む僕にとってはこれからが旅の始まりだった。
西から東へ。九州、四国、本州と、深まりつつある秋とともに僕たちの旅はつづく。

写真提供:米村奈穂
【#17に続く】
『季刊のぼろ』の話
スピーカー:米村奈穂

1974年生まれ。フリーライター。幼い頃より山岳部の顧問をしていた父親に連れられ山に入る。アウドドアーメーカー勤務や、九州・山口の山雑誌「季刊のぼろ」編集部を経て現職に。九州のハイカーのコミュニティサイト「HAPPY HIKERS」で「役に立たない道具の話」連載中。