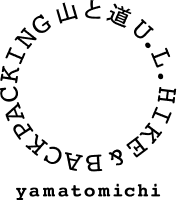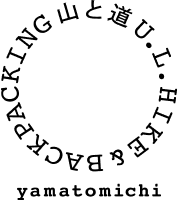ハイキングは、私たちが身体性を持って自然や世界を理解し繋がりを保つ、もしくは取り戻すために有効な方法のひとつだ。特に、より少ない装備で自然との一体感を高め、長く快適に歩こうとするULハイキングにおいてはその効果は顕著になる。
この連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』では、山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(固定概念や常識から解放され、自らの価値基準で自由に行動できるようになるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「聞く」こと、「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある価値と可能性を探っていく。
記念すべき第1回目のゲストは、アートを深く観察(ディープ・ルッキング)することで凝り固まった現実をときほぐす方法論に迫った『DEEP LOOKING 想像力を蘇らせる深い観察のガイド』(AIT Press)著者で、インディペンデント・キュレーターのロジャー・マクドナルドさん。彼のガイドで「目」という身体器官を使って「見る」という行為について学ぼうと、長野県佐久市にある彼の個人美術館兼アートセンター「フェンバーガーハウス」を訪ねた。
取材メモ:豊嶋秀樹
ロジャー・マクドナルドさんが書いた『DEEP LOOKING 想像力を蘇らせる深い観察のガイド』はアートの本ですが、「ディープ・ルッキング」を「ディープ・ハイキング」と読み替えてみても、なるほどと気づくことや納得することがたくさんありました。ディープ・ルッキングは単なるアートの批評やテクニカルな美術論ということではなくて、もっと深い世界の捉え方であったり、現代社会を生きるためのツールとして使えるんだというロジャーさんの話が、僕たち山と道の考え方にもとてもフィットしていると感じました。
単に「見えている」ということから、より積極的に「見る」ことができるようになれば、私たちを取り巻く世界や日常的な営みをより深いレイヤーで汲み取れるようになるのではないでしょうか。
みなさんもロジャーさんの著作『DEEP LOOKING』を地図に、心と身体を開いて知的探求というトレイルを歩いてみませんか? きっと、この世界とあなたのライフが今までとは違って見えるようになるはずです。
まず「ディープ・ルッキング」ってなんだ?
「アート作品を観察する」という行為を深く瞑想するための有力な手段として再発見し、この危機の時代に適応するための重要なテクニックとしても活用しようという提案。そしてロジャーさんが独自に取り組んできた研究を1冊の本にまとめたのが、『DEEP LOOKING』。

『DEEP LOOKING 想像力を甦らせる深い観察のガイド』ロジャー・マクドナルド著(AIT Press)
2,200円+税(Amazonでも購入可能)
『DEEP LOOKING』のサイト

ロジャー・マクドナルド
東京都生まれ。幼少期からイギリスで教育を受ける。大学では国際政治学を専攻し、カンタベリー・ケント大学大学院にて神秘宗教学(禅やサイケデリック文化研究)を専攻、博士課程では近代美術史と神秘主義を学ぶ。帰国後、インディペンデント・キュレーターとして活動し、様々な展覧会を企画・開催。2000年から2013年まで国内外の美術大学にて非常勤講師も行う。2010年長野県佐久市に移住後、2014年に『フェンバーガーハウス』をオープン、館長を務める。NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]設立メンバー。AITのオンラインアート講座「Total Arts Studies」ディレクター。著書『DEEP LOOKING 想像力を蘇らせる深い観察のガイド』発売中。またフェンバーガーハウスはAirbnbとして宿泊利用も可能。
フェンバーガーハウスのサイト
「深い観察」のための基本プロトコル(手順)
「最初に紹介するプロトコルは、おそらく多くの人々が部分的にでも無意識のうちにやったことがあるはずだ。それをここでは、あえて意識してやってみること。美学のように複雑なことを想像する必要はない。むしろ、規制の枠組みに囚われず、言葉にしたくなるのをじっとこらえるよう、努めることが大切だ。では、準備ができたら始めよう。」(『DEEP LOOKING 想像力を蘇らせる深い観察のガイド』より)
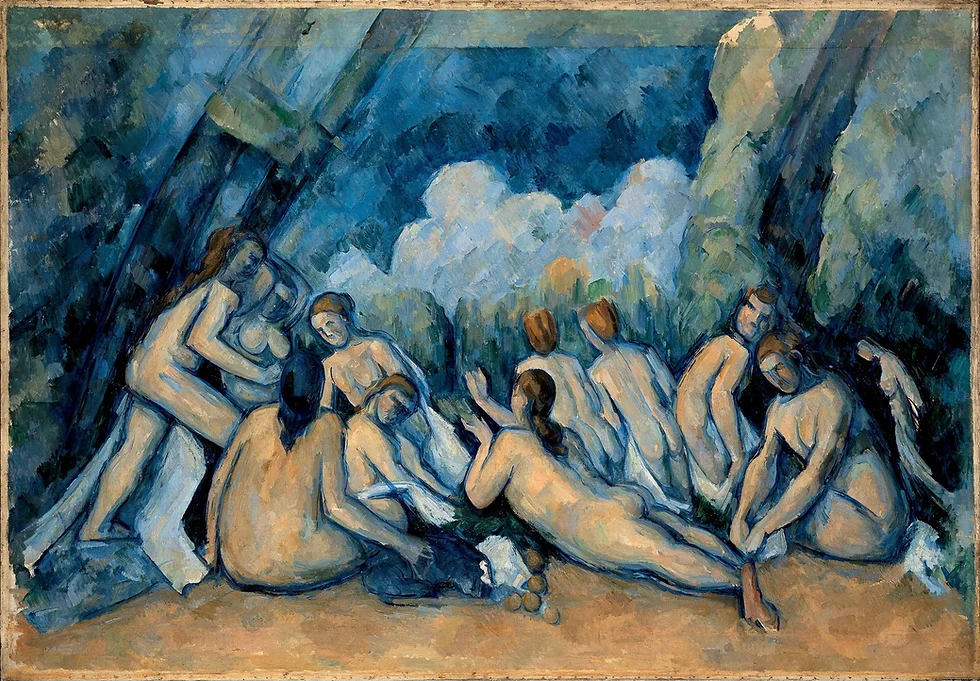
以下の手順にしたがって上の絵を観察してみよう。ひとつのフェーズにつき約5分ずつ時間をかけること。 時間が経ったら、 タイムキーパーは音で合図する。 そして、 全員で次のフェーズに移る。
1. 作品のフォルムを目で追い、 どのような作品かを確かめる
できるだけフラットな目で眺めながら、それがどんなかたちをしているか、どんな要素が含まれているかをゆっくり確認していこう。
2. 作品のパーツとパーツを関連づけていく
作品中で表された色やかたち、素材といった要素を、少しずつ丁寧に観察し、それぞれの関係性を見出していく。
3. 小さくなった自分が作品世界に入り込んでいる様子を想像する
作品のなかを実際に歩いてみよう。 自分の想像力を自由に使って、作品世界のなかでストーリーを描いてみよう。
4. 体験を共有する
ひとりで実践する場合は、用意していたノートに体験したことを書き出してみよう。 グループで行うときは、一人あたり5〜6分ほどかけて自分が感じたことを話していく。自分の体験と他者の体験を比べてみよう。

ーーまずはロジャーさんの現在までの経緯をお聞きできますか?
生まれたのは東京です。母は日本人、父がイギリスのスコットランドの人で、8歳まで東京に住んでいて、その後の学校教育はずっとイギリスでした。『ハリーポッター』のホグワーツみたいな寄宿制の学校から大学に進学して国際政治学を専攻していましたが、大学院に進んで、当時イギリスでは新しい学問だった神秘宗教学を学びました。今振り返ると、相当な勢いで神秘宗教学にのめり込んでいましたね。
その後、ずっと昔からアートも好きだったし、弟がアーティストで周りには作家の友達もたくさんいたので、自然に宗教学とアートの交差みたいなものに関心が出てきたんです。当時、そういう研究の事例はあまりなくて、神秘学とアートという私の研究は馬鹿にされることも多かったのですが、先生にも恵まれ研究論文を書き終えることができました。
日本に戻ってきてフリーランスのキュレーターとしての活動した後に、当時、森美術館の館長だった南城史生さんの事務所に入って横浜トリエンナーレに関わったり、個人のキュレーションの仕事があったり、大学で教えるようになったりして、ずっとアートワールドの中で仕事をしていたのですが、実はあまりアートワールドが自分にはフィットしてないということも感じていました。例えば大きい国際展では関わる作家の人数も予算も膨大でアートの嫌な側面も見ることになってしまうんですよね。すごく素敵な体験であったものの、僕はたぶん本来はキュレーターではなく研究者であったが故に、楽しいけれどこの世界に長くはいないかもなと感じていました。
『フェンバーガーハウス』が目指したこと

ーーそんな経緯があって『フェンバーガーハウス』を作ったのでしょうか。
大きな美術館やビエンナーレみたいな世界でやっていくことに個人的に限界があるなと感じていたこともあって、いろんな実験をしつつ自分の理想のアート体験ができるような場所として『フェンバーガーハウス』をつくりました。フェンバーガーとは大学生の時に詩などを書くときに使っていたペンネームです。すなわち空想人物の美術館なんですけど、ここでやりたいものは、ひとつは私の研究テーマであった神秘学とアートの交差。一般のアート界であまりないものなので、小さくてもいいから展覧会を企画しています。もうひとつは「ディープ・ルッキング」を実践するアート鑑賞会です。
すごくダイレクトに言うと、展覧会とは鑑賞者の体験の質を操作する装置でもあると思うんです。どうやったらその質を展覧会でつくれるのかをずっと実験しています。実験の例として、例えば長い滞在時間の鑑賞があります。完全予約制にして、私が最寄りの駅までお迎えに行き、6時間ぐらい『フェンバーガーハウス』に滞在してアート体験にコミットしてもらうというものです。「軽く拉致する」って私はよく言うんですけどね(笑)。今の美術館みたいに作品をさっと見て、ショップを通過して、カフェで1杯飲んで帰るみたいなそういう観光産業の延長線上だけではなくて、もっと違うアートとの接し方や鑑賞の仕方があるなと思っています。
宗教の勉強をしていると気付くのですが、近代以前にはいろんなアートの体験型があったはずなのに、現代の美術館はどうしてもっと多様な体験をオファーしないんだろうという疑問をいつも持っています。だいたい白い壁の部屋で作品を淡々と見るというように、同じパターンでどこに行っても同じ。まさに近代そのものの表れで単一的になってしまっているんです。でも、例えばガムラン音楽なんて軽く10時間くらい演奏している最中に鑑賞者は寝たり、食べたり、聴いたりする。アートを通じて意識を変性するっていうこともあると思います。多様なはずのものがすごく限定的になってしまっていることがすごく嫌だなと思い続けていました。『フェンバーガーハウス』はアート鑑賞の違う方法を探ってみようという実験の場所であって、ある意味リサーチセンターなんです。

ディープ・ルッキングをハイキングに置き換える
ーー最初に『DEEP LOOKING』はハイキングの本として読み換えてみてもすごく面白かったとお伝えしたのですが、ハイキングって身体行為なんですよね。ずっと歩き続けて、鳥の声や水の音を聴いたり、風を受けたりとか、ふとした時に瞑想っぽくなっている時もあるし、五感に響くんです。それこそちょっとトランスっぽい意識で自然の中に没入するハイキングという行為は、まさに『DEEP LOOKING』で語られていることとフィットするんです。
僕の中では、身体性っていうキーワードがとても大事で、ボディから鑑賞するということをもう1回再生したいっていう思いがあるんです。現代美術の鑑賞って網膜中心になっているところがあると思います。網膜と脳という非常に狭いエリアで理解しがちで、これは間違っていると思うんです。だから一度立ち止まって身体からルッキングするっていうことは、その狭くなってしまった回路をもう一度開くような意味があるので、そういう意味では身体性がすごく大切になるんです。
ーー『DEEP LOOKING』の中で「非日常的な意識状態は普段の凝り固まった思考から開放され、自由にクリエイティブに思考するための方法として有効」だと述べられていますが、この辺に関することや、「非生産的な時間を意図的に設けることには計り知れない価値がある」ということについてお聞きしたいです。そして、ただずっと絵を見るのと同じように、山をずっと歩くという行為は何もお金にならない行為だけど、それにこそすごく価値があるんじゃないかと僕も共感しました。
意識って別に固定されている状態がずっと続くわけじゃないですよね。みんな寝る時には全然異なる意識状態に自然に入るし、夢を見る時もまた違うし、ぼーっと電車の窓の外を見る時も意識状態は微妙に変わっているので、私たちの意識って常に伸び縮みしたり拡張したり、小さくなって固まったり、あるいはほぐされたりしています。それを大前提にすれば、私たちの周りにあるアートを見るのも、音楽を聴くのも、コーヒーを飲むっていうことも、摂取するもの、見るもの、起こす行動が、私たちの意識を少しずつ変えるツールとして見えてくるんです。
『DEEP LOOKING』が言っているのは、アートを見るっていうことは昔から意識をほぐす強烈な行為ではないかっていうことなんですよね。でも、鑑賞者もある程度のリテラシーとエネルギーをインプットしない限り、向こうからもらうことはできない。instagramみたいにぼーっと見ていれば何か起きるという軽々しいものではなくて、ある程度こっちも覚悟とリスクが大事だと思います。
アートを見るっていうことは、必ずしも全てポジティブで安全で素晴らしいことばかりじゃなくて、真剣に見始めると、自分の無意識とか身体性とか心理状態を揺るがす可能性も十分あります。美術館で泣き始める人もいるし、怒る人もいるかもしれないし、場合によっては一時的に精神状態が不安定になる人もいるので、アートにはそういう可能性が潜んでいるということですね。どういうプロセスでそこまで至るかっていうのが「ディープ・ルッキング」であり、そのためのガイドなんです。現代の便利な生活の中でアートがレジャー産業の延長線上のひとつみたいなものになっている中で、本来持っていた強烈な要素が排除されてきたことに対するアンチテーゼでもありますね。

ディープ・ルッキングを行う鑑賞者。(フェンバーガーハウスのウェブサイトより)
ーーアートがレジャー産業化されてきた理由は、信仰と切り離されたところに原因があるのでしょうか?
そこは大きいと思います。信仰と儀式ですね。美術館に行くっていうことは、そういう信仰とか儀式性から切り離された真っ白な世俗的な空間なので、むしろ科学の領域に近いのでしょうね。だから学芸員たちも白い手袋をして作品を持つじゃないですか。たとえば作家のアトリエに行くと、科学の領域に入る手前なので全然違う形で作品があちこちに転がっていますよね。普通に触ったり、床に置いたり、壁に置いたりしますよね。そこでは作品がまだ生活と密接に関わっているんです。でも、アトリエから出た瞬間に、急に白い手袋のゾーンに入っていって、気を付けなくちゃ!みたいになる。
美術館は残念ながらそういう要素を捨てた上で展示してしまうので、どうやってそれをつなげることができるんだろう?って考えた時に、鑑賞者がある程度のスキルやリテラシーを持って見ることで、もう一度つながることができると思うんです。「ディープ・ルッキング」はそのためのガイダンスですね。
ーー教会や寺という存在も、宗教性は置いておいても、装置としてはそういう働きを持っていたと思います。『DEEP LOOKING』でも重要な要素として書かれている「洞窟」も然りですね。
洞窟は私の中では原形的な美術環境空間なんです。だって洞窟が地球上で発見されている最も古い、私たちホモサピエンスが残した表現の跡ですからね。約4万年ぐらい前ですから。不思議なのはなぜ絵が入り口近くではなく、洞窟の奥深いところにあるのかっていうこと。大きなリスクを背負って真っ暗闇の奥深い場所に最も困難な旅をして誰かが行き壁画を残したのはなぜなのか、地球のお腹の中にあえて入っていって、なぜ表現を残そうとするのかと考えるのはすごくロマンがあるし、私にとっては美術館の原型なので、美術館は洞窟を忘れちゃいけないと思っているんですけど、近・現代の美術館って洞窟から切り離された空間ですよね。透明性を大事にするじゃないですか。
『金沢21世紀美術館』はいい例ですけど、建築的には全てがガラスでできていて、真っ白でまんべんなく光が当たって、いわゆる洞窟の奥深い場所とは真逆の感覚、空間ですよね。近代の美術館って広くて明るくて透明で、全て理性でわかるっていう感じがします。洞窟的な要素も忘れちゃダメだよと言いたいんですけど、そういう要素をどうやって今の美術館に戻せるのかなと考えたときに、もしかしたら「ディープ・ルッキング」という行為によって、鑑賞者の側で取り戻すことができるのかもしれません。

フロー状態と変性意識
ーー洞窟にはじまり、教会や寺など、意識や身体性、心理状態を揺るがす装置の代わりとして、「フロー状態(自我を忘れて物事に没頭している状態)」は機能すると思いますが、ハイキング中にはフロー状態に入る人は多い気がします。ロジャーさんが「ディープ・ルッキング」で使う時のフロー状態というのは、どういうものだと捉えているのでしょうか。
アートを深く観察すると非日常的な意識状態になってきて、例えば遊びに没頭している子どもや瞑想している時のような感覚になるのですが、このような状態を指す言葉としてフロー状態を用いています。フロー状態はアメリカの文献の中では多く言及されているし、ビジネスの世界でもすごく有効に活用されていますよね。グーグルなどの大企業では社員たちの意識をいかにフロー状態に近い状態に持っていけるかと研究していて、ワークショップや企業研修プログラムがあったりするみたいで、アメリカらしいなと思いますね。何かに没頭しているときって、フロー状態に近いと定義されていると思うんですけど、多分その体験って多くの人たちは人生で一度ぐらいはあった気がするんですよね。
ーー同じように、「変性意識」が「ディープ・ルッキング」の実践において重要な要素になると思うのですが、変性意識についても教えていただけますか?
私たちが普段、時間を多く過ごしている意識状態からの変化を指しています。例えば、普段理性が働いていて物事を聞く能力があって、返事をする能力があって、言語が使われて、ロジカルに物事をシンキングできる状態から、何らかの引き金で大きく変わる状態。だから、夢を見るという状態も変性意識状態のひとつだと思うし、フロー状態も変性意識状態のひとつだと思います。
人間の文明を見てみると、特別な儀式の中には変性意識が使われることが多いんです。制度化された宗教が登場する以前にはどの文化にもシャーマニズム的なものがあったと思います。南米の文献で読んだのですが、シャーマニズムの大事なポイントがあって、良いシャーマンは意識を激しく変性するのだけど、そのままだと良いシャーマンではないということ。良いシャーマンは必ず変性した意識をベースラインに戻すことができて、そこで得た知恵をコミュニティとシェアすることができるのだと。そこまでできてこそ良いシャーマンだというんです。
これは本当にその通りだなと思っていて、あちら側に行きっぱなしだと精神病院行きになっちゃうんですよね。重要なのは、さっきも言ったみたいに一度ベースラインに戻って、そこで体験したもの、見たもの、聞いたものを消化して新しいアイデアとしてコミュニティに共有することなんです。そうすることでコミュニティが強くなって、病を乗り越えたり、癒しの効果があるんでしょうね。これは変性意識を語るときにはすごく大切なことだと思うんです。
「トリップアウト(薬物の使用により幻覚状態になること)すればいい」では無責任で危ないと思います。近年、英語圏では60年代のカウンターカルチャーの再検証が多方面でされているのですが、サイケデリックカルチャーには賛否両論がありますね。ティモシー・リアリー(*1)みたいな人がやろうとした、LSDなどを摂取して簡単に「意識を変性しよう、それで社会が変わるんだ」というアシッドテストのような実験がありましたけど、それらはガイダンスなしでやるので、当然多くの人が精神病院に行ったわけですしね。
ーーそれはすごく重要なポイントだという気がしますよね。もちろんハイキングでは意識状態においても、実際面においても行くだけでなく、ちゃんと戻ってくる必要がありますね。
しかし同時に、1960年代のサイケデリック・カウンター・カルチャーを単に否定するのではなく、真剣に見つめ直すことも重要だと思うんです。この点で参考になる人物のひとりにイギリスの政治理論家であるマーク・フィッシャー(*2)がいます。彼は、1960年代から70年代にかけての新自由主義の台頭に対する危機感から現れたオルタナティブな政治的・社会的実践の重要な形態として、「階級意識」、「サイケデリック意識」、「意識改革ワークショップ」の3つを挙げています。
新自由主義が語るストーリーは、「現実は固定されたものであり、私たちはそれに適応し、その運命を受け入れなければならない」というものです。これは、現代人の多くが諦めを感じている理由と関係しています。フィッシャーによれば、「サイケデリック意識」は19世紀カナダの精神研究家であるリチャード・モーリス・バック(*3)が提唱した「宇宙意識」とも通じるもので、新自由主義的な考えに対抗するものだと言っています。
*1 ティモシー・リアリー
アメリカの心理学者。元ハーバード大学教授。1960年代にLSDなどの幻覚剤による人格変容の研究を行い、幻覚剤によって刷り込みを誘発できると主張し、意識の自由を訴えた。晩年はコンピューターをLSDに見立て、コンピューターを用いて脳を再プログラミングすることを提唱した。
*2 マーク・フィッシャー
イギリスの批評家。政治理論家。ウォーリック大学で博士号を取得した後、英国継続教育カレッジ、およびゴールドスミス・カレッジ視覚文化学科で客員研究員・講師を務める。自身のブログ「K-PUNK」で音楽論、文化論、社会批評を展開。著書に『資本主義リアリズム』、『わが人生の幽霊たち』、『奇妙なものとぞっとするもの』がある。2017年没。
*3 リチャード・モーリス・バック
1872年神秘体験を経験し、宇宙を「生きている存在」として鮮明に感じたバックは、それを「宇宙意識」と名付け、古今東西の様々な「宇宙意識」体験を研究し、1901年に著書『宇宙意識:人間の心の進化の研究』を発表した。彼は「宇宙意識」を人類の発達の次の段階と位置付け、最終的には全人類に広がるだろうという仮説を立てた。

治療として処方されるハイキング
ーー社会やコミュニティーの役割のひとつはお互いに面倒を見ることなんですよね。もしひとりがすごく極端な体験をすればみんなで見守る、みんなでその人のケアをするっていうことも大事なのかな。
そういうのは多分インドの文化には深く存在すると思います。インドって普通に道を歩いている人の中に「サドゥ」という、すごく悟っているんだけど、裸でウロウロしてるヒンドゥー教の行者がいるんです。何も身につけていない、お金も一切持っていない、でもそういう人は大事な人だから、周りの人がケアするという文化がインドには何千年もある。この現代の世界の中で、裸でお金がない人が歩いてるけれど、その人たちには価値があるとされる文化ってすごいですよね。インドにはいろんなタイプの意識が一緒に存在しているんでしょうね。現代はスペシャリストの時代になっちゃったから、精神病の医師とか心理学者みたいな人がいて、例えばインド以外の国で、悟りを開いていたとしても裸で歩く人がいたなら「ちょっと君この薬を飲みなさい」みたいな状況にると思うんですけど、そう考えるとすごいことだなと思いますよね。
でも、今は「社会的処方」という考え方があって、特に北欧ではメンタルヘルスの問題に関して薬治療とかではなく、アート鑑賞、あるいはハイキングが治療として処方されたりするんです。「あなたは1週間、毎日1時間歩きなさい」という処方箋のシステムができている。イギリスでは社会処方が保険のシステムの中に入っているんですよ。そういう要素がアートにはやはりあったんだ、という見直しがされているのかもしれないですよね。そういう意味でもハイキングとか、歩くという行為って、すごく大事なことだと思いますね。